【専門家に聞く!】 夜泣きに負けない 赤ちゃんとママが眠れないときの対策 第2回 「がんばりすぎるママたち。ママの睡眠は、どう確保する?」

出産を終えた多くのママたちは、ホッとするのもつかの間、赤ちゃんの夜泣きに悩み、睡眠不足を抱えて疲れきっていきます。そんなママたちのために、夜泣きのメカニズムや対策、心がまえについて、NPO法人赤ちゃんの眠り研究所代表理事の清水悦子さんに解説していただきました。2回連載でお届けします!
第1回の記事「【専門家に聞く!】 夜泣きに負けない 赤ちゃんとママが眠れないときの対策 第1回 「どうして赤ちゃんは夜泣きをするの?」」はこちら
育児ノイローゼに! 清水さんの壮絶夜泣き体験
──清水さんご自身も、娘さんの夜泣きに悩んだ経験がありますね。どのような状況でしたか?
生後6ヶ月ごろからいきなり夜泣きが始まって、1時間ごとに起こされるようになりました。さらに週2~3回、朝方2時間ぐらい泣き続けて、対策もなくてパニック状態に。精神的に追い込まれて、次第に育児ノイローゼのようになっていきました。
──まさに壮絶ですね。
冷静に振り返ると、産後うつだったと思います。日々、グッタリしていて、
「育児って、こんなに楽しくないものなんだ」
「子どもの笑顔がかわいく思えない」
「私はこんなにつらいのに、なんでこの子は笑っているの?」
なんてネガティブ思考がグルグルしてしまって……。育児疲れに睡眠不足がプラスされて、イライラが、弱い赤ちゃんへ向いてしまうのですね。
──どのようなきっかけで、夜泣きがおさまったのですか?
本を読みあさり、インターネットも使って夜泣きの対策を徹底して探したのですが、うまく解決しませんでした。そこで、海外のネンネトレーニングの中の「生活リズムを整える」ことに着目し、実践してみたら、たった5日で夜泣きがおさまってビックリ! 結局、夜泣きには半年悩まされました。
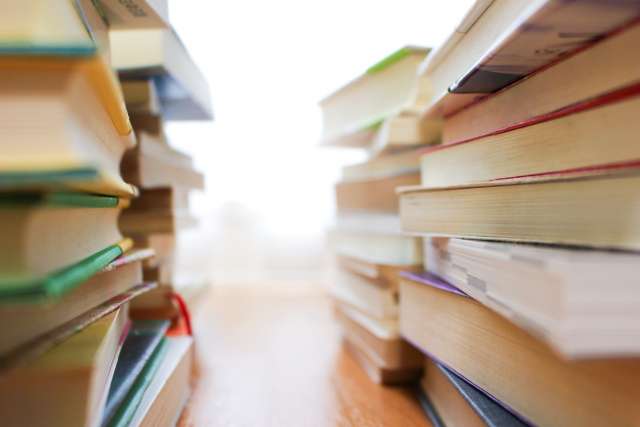
ママたちは、自分の睡眠を後回しにしがち
──同じように悩んでいるママたちは、あとを絶ちません。
産後は赤ちゃんの行動に敏感に反応する時期なので、夜中のちょっとした寝ぐずりにもママはすぐに起きてしまい、深い眠りにつくことは難しいのです。
赤ちゃんの夜泣きに気持ちが集中すると、悩みだけが膨張していきますが、自分の睡眠を確保することにも気を配って欲しいですね。
──自分の睡眠を後回しにして、がんばりすぎているママが多いのかも。
みなさん、真面目でがんばり屋です。すごく勉強熱心でもあり、あらゆる夜泣きの対策本を読んで研究しています。そのため、スタンダードな目安に当てはまらないと、「スタンダードじゃないから大丈夫?」「昨日は寝てくれたのに、今日は3回も起きて泣いた。教科書通りじゃない」などと、悩みを深くします。
SNSに広がる「楽しい育児」を、つい目指してしまう!?
──マニュアルから外れるのに不安を感じるのですね。
それだけではありません。最近のママたちは、「育児」「家事」「パパのお世話」「ママの身だしなみ」など、すべてを完璧にこなそうとしてしまう傾向があります。
赤ちゃんが夜寝てから、家事をして、パパの帰りを待って夕食のお世話をして、深夜に就寝。さらに赤ちゃんの夜泣きに付き合えば、睡眠不足になるのは当然です。
──なぜ、そこまでがんばってしまうのでしょう。
多少なりともSNSの影響はあると思います。インターネットの中には、「いつもキレイなママ」「育児と家事とパパのお世話をこなす完璧なママ」「楽しい育児」といったキラキラした世界がたくさんあります。つい、そこを目指してしまうのではないでしょうか。

──まずは、がんばりすぎる現状に気づくことが必要です。
一生懸命やるのは素晴らしいことです。でも、自分を犠牲にすると、眠れないうえ疲れも取れず、いつか身体と心を壊すことにもつながります。
夜10時に布団に入る。昼寝も有効活用して
──具体的には、どのように睡眠時間を確保すればよいのでしょう。
・ママも夜10時ごろまでには寝る。赤ちゃんと一緒に寝てしまうのも○。
・夜中に起きてしまっても、スマートフォンをいじったり、リビングへ行ったりするなど、明るい光を浴びることはせず、布団の中で静かに過ごす。
・昼過ぎくらいに、赤ちゃんと一緒に昼寝もおすすめ。30分以内を目安に、長時間寝たり、夕方以降にウトウトしたりするのは、夜の睡眠に影響が出るのでNG。
──ママの睡眠を確保するには、パパの協力が不可欠です。パパは、どのように協力するとよいですか?
・朝、出勤前にママと赤ちゃんを起こす
・赤ちゃんと遊んだり散歩したりするのは朝に
・休日も早起きして赤ちゃんのお世話を
・休日、ママひとりになる時間を作ってあげる

パパは、赤ちゃんにとって「遊んでくれる人」という認識があり、覚醒刺激が強い人。夜に赤ちゃんを起こす、8時以降にお風呂に入れる、就寝前の激しい遊びなどは控えてください。
ママがしっかり睡眠をとってこそ、夜泣きの対策と向き合える
──夜泣きで悩んでいるママたちに、メッセージをお願いします。
ときどき、「ママには母性があるから、ちょっとくらい寝なくても大丈夫だし、乗り切れる」といった専門家の意見があります。でも、そんなことはありません。まずは赤ちゃんに夜泣きがあるないに関わらず、ママがしっかりと睡眠をとれるスケジュールを確保し、心と身体を快調にすることで、冷静に夜泣きの対策にも取りかかれるのです。
パパと協力して、ママの睡眠ケアを第一優先で取り組んでみてください。
文/内藤綾子
監修:NPO法人赤ちゃんの眠り研究所代表理事 清水悦子さん
関連するキーワード

NPO法人赤ちゃんの眠り研究所 代表理事 夜泣き専門保育士
清水悦子(しみずえつこ)
大阪府生まれ。理学療法士として病院や施設に勤務後、女児を出産。生後6ヵ月から始まった壮絶な夜泣きとその改善体験をきっかけに保育士資格を取得し、夜泣きのサポート活動を開始。日本人の生活スタイルに合わせた睡眠改善方法を優しく紹介した著書『赤ちゃんにもママにも優しい安眠ガイド』(かんき出版)は、寝かしつけ育児書の定番として15万部突破。
http://www.babysleep.jp/
※記事内の写真・文章・価格・人物などは記事の更新日時点での情報となります。
現在の情報と異なる場合もございますので、ご了承ください。
大塚家具のLINE公式アカウント!
続けて読みたい!あなたにオススメの記事




















