【医師に聞く】寝ても疲れがとれないときはどうする? 前編

「しっかりと寝たはずなのにスッキリしない」「ちゃんと寝たのに疲れがとれない」など、なんとなく感じる眠りの不満。では、満足できる睡眠をとるためには、どうすればよいのでしょう。こころと睡眠学の両面からアプローチする「新橋スリープ・メンタルクリニック」の院長、佐藤幹先生にお話を伺いました。
後編の記事「【医師に聞く】寝ても疲れがとれないときはどうする? 後編」はこちら
「寝ても疲れがとれない」というのは、主観的な感覚。
—寝ても疲れがとれない原因とは?
寝ても疲れがとれない理由を考える前に、まずは十分な睡眠とは何かを考えておくことが大切です。実は、それは極めてあいまいに定義されていて、いまの時点では以下の2点が挙げられます。
①朝、スッキリと起きられること
②日中に眠気や倦怠感がなく、脳や身体が十分に機能すること
つまり、この2点がクリアできていれば、十分に睡眠がとれたと考えられているんです。ただ、この定義の内容がとても主観的ですよね。もちろん、睡眠脳波を測定すれば、深睡眠と呼ばれる深い睡眠が、どれくらい現れているかを確認することもできます。
ただし、その測定結果と主観が一致しないことも少なくありません。深い睡眠がとれていても「ぐっすりと寝た感じがしない」と感じる人もけっこういます。このかい離がどうして起きるのかは、まだ解明されていないんです。

「寝ても疲れがとれない」というお悩みも、疲れがとれているかどうかは主観的ですよね。例えば、寝ている間に何らかの非常事態が身に降りかかった場合、パッと飛び起きると思いますが、その時に寝不足でもあまり疲れは感じにくいのではないでしょうか?
非常時には、脳の報酬系というところが活性化し、覚醒することで脳が報酬を得やすい状況になります。報酬系とは、欲求が満たされたときや満たされるとわかったときに活性化し、快い感覚をもたらす神経系のこと。報酬系が活性化すると「快」や意欲向上をもたらす、ドパミンという神経伝達物質が脳内から放出されます。
「寝ている場合じゃない」となると、脳が全身に覚醒することを命令して、生理学的に目が冴えるわけですね。このことからも分かるように、起きたときにスッキリしているからといって、必ずしも客観的によい睡眠がとれているわけではないのです。
最近は、スマートフォンの便利なアプリがあるので、自分の睡眠を記録してみるのもおすすめです。よく眠れたと思う日は深い睡眠がしっかりとれていたり、十分に睡眠がとれたと思っているのに実は睡眠は浅かったり。自分の睡眠の状況を分析しながら、1〜2ヵ月くらい記録してみると、傾向がわかってきて、睡眠評価の目安になると思います。
睡眠に満足できないときは、まず時間が足りているかを確認。
—寝ても疲れがとれないと感じるときは、どうすればいい?
まず1つは、睡眠の量が足りているかをチェックしてほしいです。「寝ても疲れがとれない」と感じていても、毎日7時間以上寝ていない場合には、寝不足が大きな要因であると考えてよいと思います。
実際に「日中に眠い」と訴える人に話を聞いてみると、毎日5〜6時間しか寝ていなかったりします。自分の睡眠時間が不足していることを自覚している人は意外と少ないんです。

睡眠の必要量には、個人や年齢による違いがあります。例えば、60代より上の方なら、6.5時間程度でもよいとされています。加齢により、睡眠の要求量が減るのか、睡眠が障害されて短くなってしまうのかという問題がありますが、高齢になると、日中の活動量が低下すること、睡眠に関係の深い神経の働きが落ちること、メラトニンなど睡眠に関係するホルモンの分泌力が低下することなどが、睡眠時間減少の理由であると考えられています。
睡眠時間が自然と減ってきても、日中に元気で過ごせれば問題がありません。ただし、日中の体調不良が3ヵ月以上続く場合には、不眠症の治療が必要になります。
ところで、慢性的な睡眠不足を解消するのに何日ぐらい必要だと思いますか?
寝不足の人たちが必要な睡眠時間を知るために、「好きなだけ寝ていい」という状況を1ヵ月ほど続けた実験があります。その結果、被験者たちは、はじめの1週間ほど10時間以上寝ていたのですが、約3週間後に睡眠時間が固定されてきたそうです。
つまり、それがその人が生理的に必要としている睡眠時間だったのです。逆に言えば、寝不足を解消するためには、寝たいだけ寝ても3週間程度要するということ。慢性的な睡眠不足は、1日や2日たっぷり寝たとしても解消しないんです。
睡眠時間が足りているなら、睡眠の質をチェック。
—時間が足りているのに、寝ても疲れがとれないと感じるときは?
毎日7時間以上規則的に寝ているのに疲れがとれないなら、睡眠の質が問題かもしれません。睡眠が足りているかは、量×質で得られる面積の問題。どちらかが足りていないと、寝足りなくなります。
まずは、睡眠衛生が保たれているかどうかが大切です。睡眠衛生とは、質のよい睡眠をとるために推奨される行動や環境を整える方法のこと。厚生労働省が「健康づくりのための睡眠指針 2014」を発表して、そこに「睡眠12箇条」としてわかりやすく提示しています。眠りでお悩みの人は、エビデンスなども載っているのでぜひ読んでみてください。
読んでいただければ、例えば、寝酒の習慣や、就寝直前の高めの温度での入浴を行うことなどが、誤った睡眠衛生であることが分かります。また、「不眠だから」と言って眠くないのに早めに就寝するのも誤った睡眠衛生。それらを正すだけでも、睡眠の質がよくなることが期待できますよ。

睡眠の量がとれていて、睡眠衛生も守っていて、それでも睡眠に不満を感じるなら、病気を疑ってみることも必要です。
後編では、睡眠の質を低下させる病気についてや睡眠不足のリスク、ストレス社会と言われる現代をよりよく生きるための考え方のコツなどをご紹介します。
取材・文/武田明子
関連するキーワード
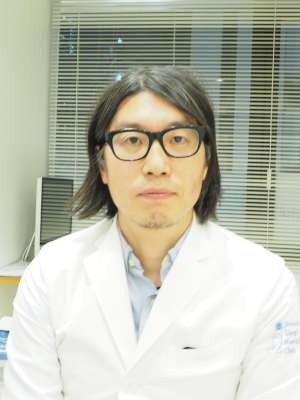
新橋メンタル・スリープクリニック 院長
佐藤幹(さとうみき)
平成9年東京慈恵会医科大学卒業、同大学精神医学講座入局。同大学付属病院本院精神科外来勤務(現在非常勤)を経て、不眠症治療(認知行動療法)の研究にて学位(博士号)取得。平成22年7月に新橋スリープ・メンタルクリニック開設。大学病院勤務中より睡眠学を専門とし、過眠症(ナルコレプシーなど)、不眠症、睡眠時無呼吸症、時差ぼけなどの臨床と研究を行い、特に不眠症に関しては認知行動療法を取り入れた治療法を研究。また、睡眠障害だけではなく、精神科領域全般(感情障害、神経症、発達障害、統合失調症など)についても広く診療を行っている。
新橋スリープ・メンタルクリニック:http://www.sleep-mental.com
※記事内の写真・文章・価格・人物などは記事の更新日時点での情報となります。
現在の情報と異なる場合もございますので、ご了承ください。
大塚家具のLINE公式アカウント!
続けて読みたい!あなたにオススメの記事




















