不眠体質に合った漢方で、やさしく改善 第2回
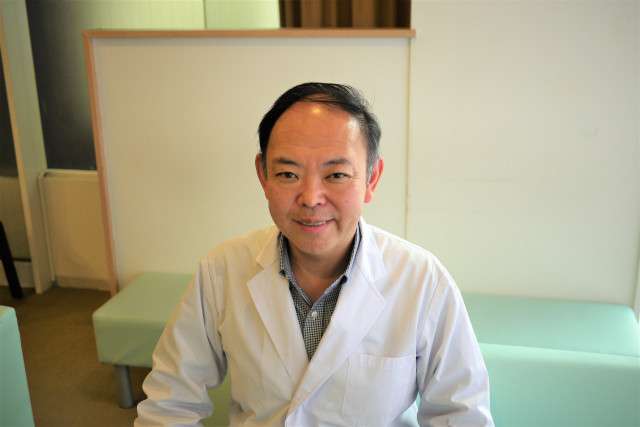
「ぐっすり眠れない」「寝つきが悪い」といった睡眠の悩みを持つ人は、東洋医学の観点から見た「不眠になりやすい体質」かもしれません。そこで、さまざまな不調を呼ぶ体質の改善に詳しい、代官山パークサイドクリニック院長の岡宮裕先生に、睡眠トラブルに関する情報や、漢方薬で改善を目指す方法などを2回連載で教えていただきました。
第2回は、不眠を改善するための日常生活の注意点などについて解説します。
第1回の記事「不眠体質に合った漢方で、やさしく改善 第1回」はこちら
実証(じっしょう)・虚証(きょしょう)ともに生活習慣の見直しを
※実証・虚証についての詳しい説明は第1回目の記事をご覧ください
──診察では、不眠の人へどのようなアドバイスをされていますか?
その方に合った漢方薬を処方しますが、同時に必ず日常生活の見直しをはかるように促します。生活習慣が乱れて睡眠リズムが崩れ、不眠につながっていることが少なくないからです。
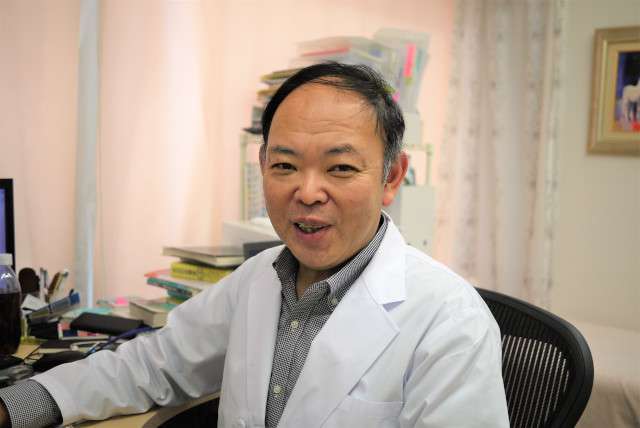
──具体的には、どのような指導をされているのでしょう。
次のことを、なるべく実践していただくようにしています。
朝起きる時間を一定にする
平日が忙しいと、週末寝だめをしてしまう人が目立ちます。それでは睡眠リズムが乱れるのは当然です。最初は夜更かししてもかまわないので、休日の朝もいつもと同じような時間帯に起きることを心がけてください。早起きが習慣づいてくると、休前日の早寝も身についてきます。
昼寝をしない
夜にきちんと眠気が訪れるように、昼間はアクティブに行動して夜の睡眠に備えましょう。一日の中でメリハリのある生活が大切です。
寝る前に強い光を浴びない
パソコンやスマートフォンから出る強い光を浴びていると、交感神経が活発になったままとなり、眠りのモードへ入りづらくなります。夕食後は、なるべくIT機器から離れてゆっくりと過ごし、そのままベッドへ入ることをおすすめします。
誤った入眠儀式をつくらない
ときどき、「アルコールを飲まないと眠れない」「甘いおやつを少しだけ食べてからベッドへ入る」など、睡眠や健康にとってよくない入眠儀式を実践している方がいます。特にアルコールは眠りが浅くなるうえ、利尿作用があるので夜中にトイレへ立つ回数が増えることもあります。
本来の入眠儀式は、入浴をする、アロマを炊く、ストレッチをするといったことで、寝つきをよくして深い睡眠へと導いてくれるものです。上質な睡眠を促す入眠儀式を探しましょう。
朝起きたら太陽の光を浴びる

朝起きたら窓を開けて、太陽の光を浴びてください。目に光が入ってくると、体内時計がその日のリズムを刻み始めます。昼間に活動し、夜に眠気が訪れベッドへ入るというメリハリのある生活は、朝一番の光のシャワーから始まります。
生活習慣の見直しは、実証と虚証における不眠体質の違いにかかわらずすべての患者さんにアドバイスしています。改善されれば、漢方薬の効果を十分に受けることができます。
気軽に刺激! 頭頂部のツボ
──東洋医学ではツボ刺激も推奨されていますが、睡眠によいとされるツボはありますか?
「百会(ひゃくえ)」というツボは、全身の気を補い、ストレスやイライラを解消するのに役立つと言われています。気持ちを安定させて深い睡眠へと導いてくれるでしょう。頭頂部の位置にあるので、「気持ちよい」と感じる程度の強さで刺激してみてください。
──ところで、先生ご自身の睡眠に対する考え方をお聞かせください。
質のよい睡眠がとれているだけで、気持ちが安定したり、仕事が効率よくはかどったりします。また、不眠は病気の引き金になることがある一方で、十分な睡眠は病気の予防につながります。睡眠は、生きていくためになくてはならない基盤だと感じます。
岡宮先生の「癒やされる!」入眠儀式とは?
──先生ご自身の睡眠に対するこだわりは?
冬は、入浴をする、寝室を暖めるなど、身体を冷えから守るように気を配っています。人は夕方から夜にかけて体温が上がり、手足や身体の表面から放熱されることによって体温が下がって眠くなります。
ところが身体に冷えがあると、このような体温調整がうまく行われず、質の悪い睡眠へとつながってしまうのです。特に虚証の人の不眠は冷えを抱えていることが多いうえ、東洋医学で冷えは万病の元とされているので注意が必要です。
また、寝具に気を配ることも重要です。私の場合、寒さが厳しくなるこれからの時期は、あったか機能の高い季節寝具を使用しています。寝室内を整理整頓して、あまり物を置かないようにすることにも気をつけています。
──先生の入眠儀式はありますか?

ペットのヨークシャーテリアと、寝る前に遊ぶことが入眠儀式になっているかもしれません。必ず、「寝る前に遊んで欲しい」とじゃれてくるのですが、その遊んでいる時間が癒やしとなって一日の疲れが抜けていきますね。
不眠に寄り添う漢方薬。いつでも相談を
──微笑ましいですね! 最後に、読者へメッセージをお願いいたします。
特に虚証で不眠の人は、「眠れないと大変なことになる」「○時間寝なければいけない」など、自分にプレッシャーをかけてクヨクヨ悩んで眠れないことがよくあります。「なんとしても寝なければ」と気負わないことが大切です。不安感が強いときは、自分に合った寝具を揃える、寝室をすっきりと片づける、カラーコーディネートをするといった環境づくりだけでも、気持ちがリフレッシュして睡眠へのアプローチになります。
そのうえで、不眠に悩んだときはクリニックを受診し漢方薬で改善をはかることもひとつの方法です。いつでも相談に来てください。
取材・文/内藤綾子
監修:代官山パークサイドクリニック 岡宮 裕(おかみや ゆたか)先生
関連するキーワード
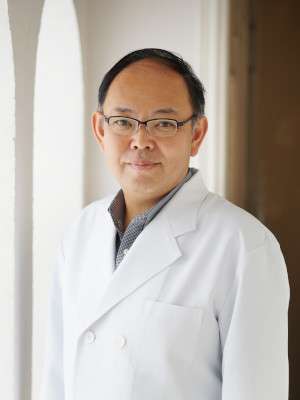
代官山パークサイドクリニック
岡宮裕(おかみやゆたか)
1990年、杏林大学医学部 卒業。慶応義塾大学腎臓内分泌代謝内科に入局。腎臓病・高血圧・糖尿病などの診療に従事した後、横浜市立市民病院・静岡赤十字病院・練馬総合病院などに勤務。2009年、代官山パークサイドクリニック開業。「身体に負担の少ない、一人一人に最適な治療」を心がける。2011年、海外渡航前医療センター開設。スポーツドクターとしても活動。
https://www.parksideclinic.jp/
※記事内の写真・文章・価格・人物などは記事の更新日時点での情報となります。
現在の情報と異なる場合もございますので、ご了承ください。
大塚家具のLINE公式アカウント!
続けて読みたい!あなたにオススメの記事




















