不眠体質に合った漢方で、やさしく改善 第1回

「ぐっすり眠れない」「寝つきが悪い」といった睡眠の悩みを持つ人は、東洋医学の観点から見た「不眠になりやすい体質」かもしれません。そこで、さまざまな不調を呼ぶ体質の改善に詳しい、代官山パークサイドクリニック院長の岡宮裕先生に、睡眠トラブルの情報や、漢方薬で改善を目指す方法などを2回連載で教えていただきました。
第1回は、不眠になりやすい体質についての情報をお届けします。
第2回の記事「不眠体質に合った漢方で、やさしく改善 第2回」はこちら
日本人の38%が不眠に悩んでいる
──現在、睡眠に悩む人は、どれくらいいるのでしょうか?
平成25年の調査によると、日本人の38%が不眠に悩んでいるという報告があります。5人に2人が該当するという高い数字で、多くの人が睡眠について悩んでいることがわかります。
──不眠を放っておくと、どのようなデメリットがありますか?
昼間ボーッとして仕事がはかどらない、前日の疲れがとれないといったことが起こり、不眠症の人は仕事の効率が3割落ちると言われています。その他、基礎代謝が低下する、精神的に不安定になりイライラが増す、落ち込むなどということも。精神面に影響が大きいと、うつ病につながることが珍しくありません。
うつ病によって不眠症状がひどくなり、さらにうつ病を悪化させるという悪循環になることもあります。「たかが不眠」と侮らず、早めに改善を目指すことが必要です。
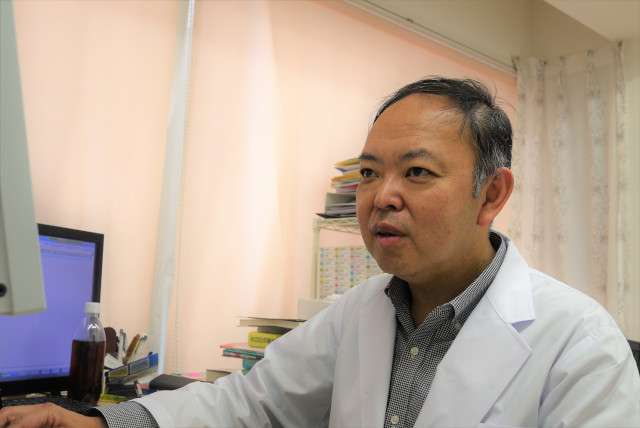
漠然と不安を抱えるクヨクヨ不眠が多い
──日々の診療の中で、睡眠に悩む人の傾向があれば教えてください。
睡眠の悩みを抱える人は、身体の調子が悪い、寝具が合わない、睡眠環境が悪いなど、いくつか理由があります。そんな中、患者さんと向き合っていると、不安や悩みを抱えて眠れない人が多い印象を受けます。それを大まかに分けると、2つのタイプになります。
タイプ1.漠然とした不安を抱えるクヨクヨ型の不眠……“漠然とした不安”にさいなまれて、満足に眠れないというクヨクヨ型が目立ちます。“漠然とした不安”とは、「年金が破綻したらどうしよう」「自然災害が来たら、家は大丈夫?」といった「抽象的な不安」のこと。現代の日本の社会情勢や環境変化が、大きく影響していると思われます。

タイプ2.具体的な不満を抱えるイライラ型の不眠……「今朝の上司の説教にムカムカした」「ご近所の奥さんから、不愉快なことを言われた」など、具体的な出来事を思い出して腹が立ち、興奮して眠れないタイプです。
不眠になりやすいのは虚証の人
──東洋医学の観点から、睡眠トラブルを抱えやすいのはどのような人ですか?
「証(しょう、あかし)」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。その人の身体・体質・見た目・かかりやすい病気の特徴のことです。東洋医学の診察では、問診などから「証」を見極めて不眠患者さんに合った漢方薬を処方します。
漢方では、3つの体質にわけることができます。
・実証(じっしょう)……体力のある人
・虚証(きょしょう)……虚弱な人
・中間証……実証と虚証の間に位置するバランスのとれた人
上記で紹介しているクヨクヨ型の不眠体質の多くは虚証の人です。「気」という生命エネルギーの流れが滞りがちで、ストレスや不安を抱えるといつまでも引きずってしまい、睡眠や覚醒のリズムが乱れやすいのです。一方、イライラ型の不眠体質は実証の人に多く見られます。
不眠の体質に合わせて漢方薬を選ぶ
──不眠体質に合わせた、代表的な漢方薬を教えてください。

実証の不眠に
・柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)
イライラや興奮を鎮めます。日中は元気で、怒りっぽくイライラが強い人向き。興奮して眠れない、働きすぎて眠れないといったケースに。
・女神散(にょしんさん)
血行を促進し、気の巡りをよくします。ホルモンバランスの乱れによって起こる不眠に強い薬。更年期障害の改善にも使われ、女性に適しています。
・抑肝散(よくかんさん)
肝の高ぶりを抑え、高ぶった神経を鎮めます。イライラやカーッとなりやすい衝動性を抑えるので、興奮して眠れないときに役立ちます。
虚証の不眠に
・加味帰脾湯(かみきひとう)
精神的にストレスが多く、うつ症状や不安感があるときに効果的。クヨクヨ型の不眠の場合によく処方されます。
・酸棗仁湯(さんそうにんとう)
精神不安や神経過敏などのメンタル的な病気によく使われます。気持ちを安定させるのに、効果を発揮。生活リズムの乱れなどから疲れて眠れない人に。
・加味逍遥散(かみしょうようさん)
ホルモンバランスを整える効果が高く、女性の更年期障害で不眠症状が現れた場合に処方されることが多いです。
・桂枝加竜骨牡蛎湯(けいしかりゅうこつぼれいとう)
ストレスが主な原因で引き起こされた不眠症や、うつ病などの症状を軽減します。不安定な気持ちを落ち着かせる作用があり、眠りが浅いときなどに有効。
──「不眠」とひと言で言っても、これだけの漢方薬があるのですね。西洋医学の「睡眠薬」とはまったく違います。
西洋医学では、病名に適した薬を選ぶので、同じ病名の人には同じ薬が用いられます。一方、東洋医学では症状や体質などを見極め、その人の証(体質)にあった漢方薬を処方します。不眠の改善を目指すなら、オーダーメイドで身体に無理なく作用する漢方薬がピッタリです。
第2回は、不眠体質を改善するための、日常生活の注意点などについて解説します。
取材・文/内藤綾子
監修:代官山パークサイドクリニック 岡宮 裕(おかみや ゆたか)先生
関連するキーワード
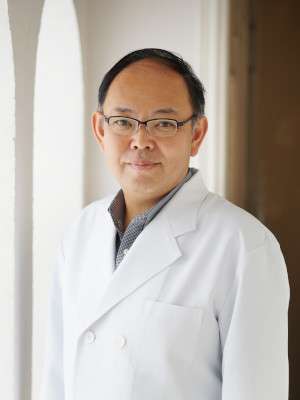
代官山パークサイドクリニック
岡宮裕(おかみやゆたか)
1990年、杏林大学医学部 卒業。慶応義塾大学腎臓内分泌代謝内科に入局。腎臓病・高血圧・糖尿病などの診療に従事した後、横浜市立市民病院・静岡赤十字病院・練馬総合病院などに勤務。2009年、代官山パークサイドクリニック開業。「身体に負担の少ない、一人一人に最適な治療」を心がける。2011年、海外渡航前医療センター開設。スポーツドクターとしても活動。
https://www.parksideclinic.jp/
※記事内の写真・文章・価格・人物などは記事の更新日時点での情報となります。
現在の情報と異なる場合もございますので、ご了承ください。
大塚家具のLINE公式アカウント!
続けて読みたい!あなたにオススメの記事




















