【スペシャリストに聞く】冬の眠気の原因と解消法は? 第2回目
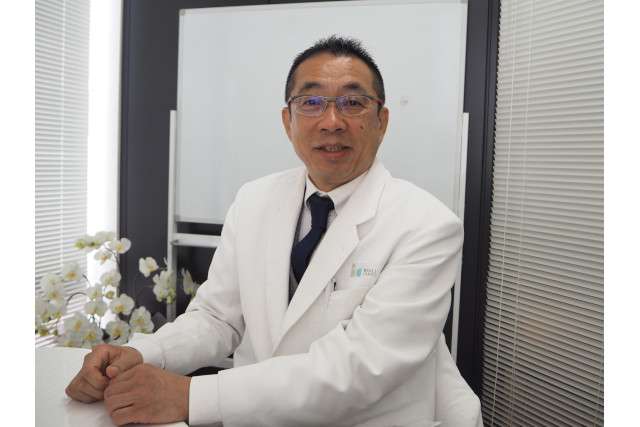
「ベタースリープ、ベターライフ」を掲げる心療内科『ベスリクリニック』の田中伸明院長に聞く連載記事。第一回目では、冬の眠気や過眠、過食、やる気低下などの冬のうつっぽい症状は、自然な生態リズムによるものだというお話を伺いました。そこで、第二回ではそれらの予防法についてアドバイスしていただきます。
第1回の記事「【スペシャリストに聞く】冬の眠気の原因と解消法は? 第1回目」はこちら
朝の光と日中の運動で、冬の眠気を予防する。
—朝の強い眠気など、冬のうつのような症状を予防するには?
実は、すごく当たり前のことをするだけなんです。
まずは、毎日定時に起床して、起きたらすぐに光を浴びること。第一回でお話ししたように、私たちは光を浴びることで、脳内に抗うつ物質と呼ばれるセロトニンの量が増え、睡眠ホルモンであるメラトニンの量が下がるようにできています。さらに、起床したらカーテンを開けて光に当たるようにしましょう。窓辺で朝の歯みがきをしたり、日の当たるリビングで朝食を摂ったり、ゴミ出しに外に出るなどもおすすめです。
さらに、日中にもできるだけ光を浴びることで、セロトニン量を上昇させることができると言われているんです。ちなみに、セロトニンは目の網膜が光の刺激を受けることで減っていきます。一般的には光を浴びるという表現を使うので、肌から光を吸収するようなイメージもありますが、厳密には光を浴びるというより目で光を見るという方が正しいですね。

2つめのポイントは、日中にしっかり運動をすること。運動をすることで脳内に喜びの神経伝達物質であるドーパミンが増えると、より元気になることが期待できます。また、日中の活動量を上げることで、睡眠の質を上げることにもつながります。
冬場なら、光がまぶしくてサングラスをかけたくなるような遊びをするのもよいですね。例えば、スキーやトレッキング、サイクリングなど。冬場の楽しい遊びをすることで、自然と日中に光を浴びられます。

3つめは、睡眠負債を貯めないこと。つまり、睡眠不足の状態を継続させないこと。睡眠不足になると精神が不安定になるので、抗うつやパニック発作など、もともと持っている性質や症状が表面化しやすくなります。また、睡眠負債が貯まると、休日に睡眠不足を補おうと昼まで寝てしまったりしますよね。そうすると、睡眠のリズムが狂って、月曜の朝に強い眠気を感じて、最悪は出社できないということもあります。
朝はバナナ&牛乳で、抗うつ物質のセロトニンをアップへ。
—予防のために、食事にも気を配ったほうがいいですか?
4つめのポイントは、やはり食事ですね。
睡眠物質であるメラトニンは、光を浴びることで抗うつ物質であるセラトニンに変わるのですが、そのメラトニンの原料となっているのが、トリプトファンという必須アミノ酸。これは、私たちの体内では作りだすことができないので、食事で摂ることが大切なんです。光を浴びるだけでなく、普段の食事でトリプトファンが含まれる食材を多めにとることを心がけてほしいですね。
私のクリニックには『セロトニンセラピー』というものがあって、食事指導なども行っています。トリプトファンは、たんぱく質に含まれているので、肉類や魚介類、レバー、豆腐、牛乳、チーズ、あとはバナナや海苔などもおすすめです。クリニックの患者さんには、バナナをいつも準備してもらって、朝食に摂取するようアドバイスしています。

患者さんを見ていると、特に若い世代の人たちは食生活が乱れがちなようです。神経伝達物質の原料となるトリプトファンなどをきちんと摂取できていなくて、うつ状態になりやすいのではないかと感じています。さらに女性は、第一回でもお話ししましたが、生態リズムの感受性が高いので冬季うつになりやすいんです。20代の女性が冬季うつになりやすい傾向があるのは、感受性が高いことも理由のひとつだと思います。
自然の光を浴びられない場合は、ライトの光を。
—光を十分に浴びられないような環境の場合は?
冬季うつの症状を軽減するには、基本的には光を浴びることが大事。朝起きたら太陽の光を浴び、日中も太陽の光のもとで活動するのが一番ですが、それができない人もいますよね。例えば、シフトの都合で昼夜が逆転するような場合。または、冬場に晴れ間の少ない地域や日照時間の短い地域の人。そういうときは、専用のライトを活用する治療法があります。

高照度光療法と呼ばれるものですが、私のクリニックではスマホサイズのライトを使っています。約1万2000ルクスの高照度光を、5〜20分くらい浴びてもらうんです。これは、冬季うつの患者さんだけでなく、どなたでもセロトニンを増やすために使っていただいて大丈夫。似たような商品も市販されているので、ご自身で買っていただいてもよいと思います。
ライトを浴びるタイミングとしては、起床時に浴びるのがよさそうなイメージですが、夕方でも効果があると言われています。
もしくは、蛍光灯の光を浴びるのでもよいです。直接光を見るのではなく、光の近くで本を読んだりしてみてください。
睡眠をコントロールして、より良い人生を。
—最後に、田中院長の快眠法を教えてください。
お酒を飲みすぎないことでしょうか(笑)。でも、やはり一番のポイントだと思っているのは、土日の過ごしかたです。
平日は夜9時頃まで診療をしているので、どうしても就寝が遅くなり睡眠のリズムも後ろに移動してしまいます。仕事の後に食事に行って就寝時間が遅くなることもあるのですが、それでも起床時間は揃えて規則正しい生活を心がけていますね。そして、休日も平日と同じ時間に起きて、太陽の光の下で活動するようにしています。
私は毎日、睡眠日誌をつけているんですが、そうすると睡眠時間だけでなく、自分の生態リズムも分かってきます。例えば、夏は睡眠時間が短く、冬は長くなっていることも見えてくるんです。また、「休日に夜更かしして遅く起床したせいで、睡眠が乱れがちだな」といったことも分かります。
自分の睡眠を知ることができるので、睡眠日誌をつけるのはどんな人にもおすすめです。日中にどのタイミングで眠気を感じるかをメモしておくと、対策もたてやすくなります。例えば、冬になると強い眠気を感じているなら、冬季うつの症状が出ているのかもしれません。
また、起床後4時間後に眠気が出るようなら、睡眠負債を抱えている可能性が高いんです。それが分かれば、睡眠時間をしっかりと確保したり、運動をして睡眠の質が高くなるように心がけたり、調整をすることができますよね。
「ベタースリープ、ベターライフ」という想いで、私はクリニックの名前をつけました。睡眠は、より良い人生を送るための手段。人生そのものが良くなるよう、ぜひ、睡眠をご自身でコントロールしてください。
取材・文 武田明子
関連するキーワード

心療内科・メンタルクリニック『ベスリクリニック』院長
田中伸明(たなかのぶあき)
日本神経学会認定医、日本東洋医学学会専門医、医師会産業医。
鹿児島大学医学部卒業。神経内科専門医を取得し、諏訪中央病院(鎌田実院長)で地域医療に従事、その後厚生労働省で行政を、外資系コンサルティングファームでマネジメントを学ぶ。 その経験をもとに、会津大学理工学部、京都産業大学経営学、日本大学工学部の教授として大学教育に従事。
日本を支えるビジネスパーソンのメンタル障害を解決することが重要と考え、投薬治療を前提としない心療内科・メンタルクリニック『ベスリクリニック』を開設。
著書に『「病院経営を科学する!」(遠山峰輝・堤達郎共著/日本医療企画) 『田中教授の最終講義』 など。http://besli.jp
※記事内の写真・文章・価格・人物などは記事の更新日時点での情報となります。
現在の情報と異なる場合もございますので、ご了承ください。
大塚家具のLINE公式アカウント!
続けて読みたい!あなたにオススメの記事




















