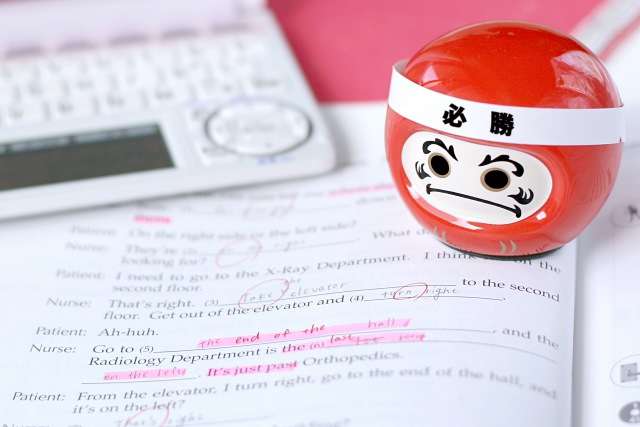睡眠不足を改善して日中の活動や仕事の効率をアップする(前編)

毎日なぜか疲れがとれず、やる気が出ないし仕事にも集中できない…。そんな状態に陥っている人はいませんか?
実はその原因は睡眠不足にあります。日中の活動を充実させるためには質のよい睡眠が欠かせません。とはいえ、睡眠の大切さを理解できてはいても、いざ実践しようと思うと難しいものです。
「仕事のストレスをなくす睡眠の教科書」(方丈社)の著者であり、全国で睡眠マネジメントの講演を行なっている和田隆さんは「睡眠改善とは、なぜ眠れないのか、自分が抱える睡眠の問題をまず知ることが大切」だと言います。さあ、日中の活動や仕事の効率をアップさせるべく、睡眠マネジメントをスタートさせましょう!
後編の記事「睡眠不足を改善して日中の活動や仕事の効率をアップする(後編)」はこちら
睡眠不足の改善で仕事のパフォーマンスを劇的にアップ
和田さん:生きていく上で、知識や技術を習得したり、豊かさを得るためのアプローチは人によってさまざまです。しかしながら、睡眠というのは生き物すべてに必要なものであり、睡眠不足はすべての意欲を低下させます。睡眠不足に陥ると、普段やっていることができなくなり、ネガティブマインドになってしまいます。
実は僕自身が“睡眠改善すると人生が変わる”ということについて、身をもって体感しました。30代は毎日睡眠時間もバラバラで完全に夜型でした。夜になると調子が出てきて、寝る時間は1時過ぎ。週末は朝方まで起きていました。毎日調子が悪いのが普通だったので風邪ばかりひいていましたし、何度も入院しました。当然仕事のパフォーマンスは下がりますし、負のスパイラルに陥っていました。
あるとき、これではいけないと思い、自分がなぜ眠れないのか、眠れない原因を徹底的に探ることにしたんです。僕の場合はテレビが原因でした。寝ても覚めても観ているほどテレビが大好きだったのですが、それが原因で睡眠不足になっていることに気づき、思い切ってテレビを捨ててみたんです。
そうすると時間の使い方が変わり、驚くほどライフスタイルが変化しました。極端かもしれませんが、テレビを見ていた1時間を、睡眠のための時間としたことで、日中の仕事のパフォーマンスが格段に上がったのです。そして、土日に寝だめをやめて平日と同じ時間に寝て同じ時間に起きることを実践しました。これだけで50代になった今でもまったく風邪をひきません。便利なものを捨てたときに、一番大切なものを獲得できたのです。
ストレス順位表でストレスを管理する

和田さん:現在、睡眠に関する情報は本にもインターネットにもあふれています。しかし、その多くは睡眠のメカニズムの説明や寝具や寝室などを含めた眠りによい環境づくりについての説明です。睡眠の改善策として「行動に移すこと」「継続させること」の重要性については書かれていないことが多いです。
快眠の方法を頭で理解することは難しくありません。しかし、実践、継続することこそが難しいのです。睡眠の問題は、睡眠以外の領域へのアプローチが必要です。具体的にはストレスマネジメント、感情マネジメント、行動マネジメントを取り入れた「睡眠マネジメント」の実践が睡眠改善につながるのです。
現代社会は睡眠を阻害する要因があまりにも多く存在します。日々の睡眠を適切に管理しないと本来の自然な眠りを取り戻すことはできません。まずは快眠を妨げる最大の要因ともいえるストレスからはじめましょう。
ストレスにはよいストレスと悪いストレスがあります。大きな仕事にチャレンジするときに、プレッシャーはあるけれど好奇心をもってやりたいと思えているのならそれはよいストレスなので問題ありません。睡眠を阻害するのは悪いストレスです。たとえば騒音は誰にとっても悪いストレスですよね。悪いストレスがあると、そのストレスに囚われて考え事をしてしまいます。その際、覚醒物質が分泌されて自律神経である交感神経が優位になってしまい、寝つきが悪くなってしまうのです。
心や身体にストレスを感じ続けていると自律神経を乱す原因となるので、ストレスを溜め込まないように日ごろから自分なりのリフレッシュを実践することや、ストレスの要因となっている問題を早期に解決することが重要です。
私が推奨しているのは「ストレス(私の悩み)順位表」を作成することです。今自分を悩ませていることを1位から10位までランキングしてみるのです。
このときに、単に「仕事」とか「人間関係」と書くのではなく、できるだけ悩んでいる内容を具体的に書いてください。「ストレス」や「悩み」と言った抽象度の高い問題を分解すれば、対処できる問題と対処できない問題が明確になります。そして、その内容が仕事上のことか、プライベートなことなのかもわかるようにしておきましょう。こうすることで、仕事と私生活のバランスや偏りに気づくこともできます。
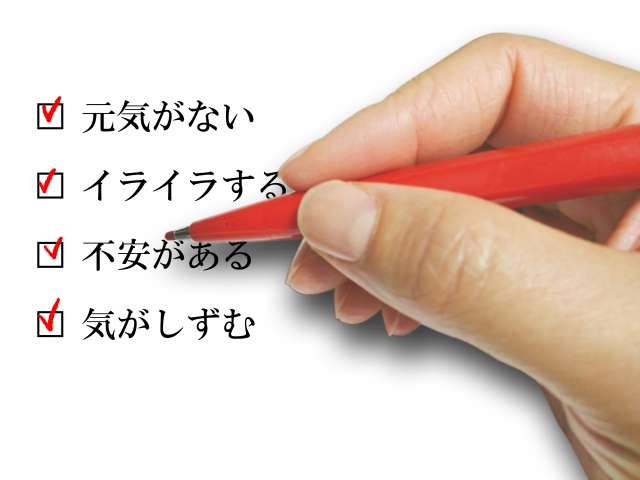
ストレス管理表を書き出したら、小さいストレス(10位)から解消していきます。下位の問題は解決しやすいので、積極的にどんどん減らしていくことを心がけましょう。
下位にランキングしやすい強度の低いストレスの例
・ 片付いていない部屋
・満員電車や長い通勤時間
・近所の騒音
・部屋の温度、湿度
・夫や妻の愚痴
上位にランキングしやすい強度の高いストレスの例
・離婚
・リストラ
・転職や異動
・ハラスメント
・介護
下位のストレスをひとつずつ解消できたとして、最後に残る1位の悩み。これを解決するのはなかなか難しいと思います。一番に書いた悩みは「解決の方法がわからない」「解決できないと認識している」から一位なのだと思います。私たちはすぐに解決できる問題で深く悩むことはありません。
ではどうすればよいのか。
「他者のサポートを受けて問題に対処する」ことです。責任感の強い人はなんでも自分で解決しようとするのですが、実は問題解決能力が高い人というのは、誰かに相談できる人、すなわち、相談する能力の高い人なのです。
他者は客観的に問題を分析し、選択肢やあなたにはない解決に役立つスキルを持っています。もし問題を解決できなかったとしても、問題を小さくすることができるので、一番の悩みではなくなるのです。あなたの周りにはあなたを助けてくれる人がいます。勇気を出して「困っています。助けてください」と打ち明けてみてください。その瞬間あなたの問題解決能力は飛躍的に上がります。「問題解決能力の高い人とは、自力で解決することに執着しない人」です。
身体の不調であれば医師、介護なら介護支援専門員、法律問題は弁護士、心の悩みはカウンセラーなど、困っている問題に対して専門家がサポートしてくれます。
上位の悩みを解消するには時間がかかるかもしれませんが、諦めずに人のサポートを受けながら実践してみてください。小さなストレスを解消するだけでもスッと気分が晴れやかになるものです。ストレスをなくして睡眠不足を解消し、日中の活動や仕事のパフォーマンスを上げることを目標に頑張りましょう。
メンタルヘルスを支援する専門家として、民間企業や官公庁などで多くの講演を行ってきた和田さんならではの「睡眠マネジメント」。前編は「ストレスマネジメント」のお話でした。ストレス管理表を作成するだけでも心の悩みが整理されて、次にやるべきことが見えてきますよね。後編では「行動マネジメント」と「感情マネジメント」についてお話を伺います。
取材・文/横田可奈
関連するキーワード

メンタルプラス株式会社 代表取締役 ウェルリンク株式会社 シニアコンサルタント
和田隆(わだたかし)
カウンセラー、EAPコンサルタントとして、職場のメンタルヘルスとハラスメント防止を支援。カウンセリング、キャリアコンサルティング等、相談実績は6,000件以上。大手企業を中心に教育委員会、官公庁、病院等に対し、講演、研修の出講実績は1,500回以上、受講者は10万人を超える。
著書
・ 『仕事のストレスをなくす睡眠の教科書』(方丈社)
・ 『パワハラをなくす教科書』(方丈社)
※記事内の写真・文章・価格・人物などは記事の更新日時点での情報となります。
現在の情報と異なる場合もございますので、ご了承ください。
大塚家具のLINE公式アカウント!
続けて読みたい!あなたにオススメの記事