【医師監修】睡眠不足が続くとどうなる?健康への影響は?

日本人の睡眠時間は世界的に見ても、とても短いことが調査から明らかになっています。しかも年々、その睡眠時間は短くなる傾向にあります。また、睡眠不足であるにもかかわらず、それを自覚していない人も少なくありません。午前中に眠気が起きるようであれば、それは睡眠不足の可能性が高いでしょう。
他にもどんな状態が睡眠不足なのか、どうすればそれが解消できるかを、不眠で悩む患者さんも多い「ナチュラルクリニック代々木」の野本裕子院長にお話を伺いました。
そもそも睡眠不足ってどんな状態?
人が生きていく上で、食事とともに必要なのが睡眠です。睡眠には、昼間の活動で疲労した身体を回復させる役割があります。脳を休ませ、自律神経を整えると同時に、昼間に得た情報を整理する働きもあります。ところがいろいろな要因で、身体が回復するのに必要な睡眠時間の量が足りなくなったり、時間は足りていても熟睡が出来なかったりと、睡眠の質が悪くなることがあります。こうした状態を総じて睡眠不足と呼びます。
昼間の活動のパフォーマンスが低下
身体に必要とされる睡眠が不足すると、昼間の活動に影響が現れます。「まず、日中に強い眠気が起きる人が多いですね。眠気を感じているなら睡眠不足を自覚できますが、気づかない人もいます」と野本医師。睡眠不足にもかかわらず、それが自覚できていない人でも、実は昼間の活動パフォーマンスが低下したり、身体に不調が現れたりなど、睡眠不足の影響が見られるとのこと。

「活動パフォーマンスの低下とは、例えば、集中力が低下して、いつもこなせている仕事量が十分にこなせなくなったり、注意力が散漫になるせいで、聞き漏れが増えてしまったりと、いつもと同じ力が発揮できなくなることです。自覚せず、極めて短時間の意識消失が起きていることもあります。」(野本医師)。
睡眠不足の影響から、あらゆる身体の不調が現れる
寝不足による身体の不調には、頭痛やめまい、目の裏の痛み、頭がーっとする、身体がだるい、吐き気がするなどの症状のほか、記憶力や思考力が低下したり、不安になったり憂鬱になったり、ストレスを感じやすくなったりなどが挙げられます。
「適切な睡眠時間は、個人差があるので一概には言えませんが、一般的に6時間以下の睡眠は、時間が足りていないとされています」と野本医師。短い睡眠しかとらなくても健康でいられるショートスリーパーと呼ばれる人たちは、実際にはほとんどいないそう。
自分にとって、最適な睡眠時間を知るには、休みの日に、朝になっても室内が明るくならない部屋で、目覚ましをかけずに寝て、自然に目が覚め、すっきり起きられたときの睡眠時間を参考にします。最近では、自分の睡眠サイクルを調べるスマホのアプリもあるので、それらを利用するのもよいでしょう。
ぐっすり眠れている人の睡眠サイクルは?
自律神経が正常に働くとよい睡眠に
睡眠は疲れた身体をリセットして、翌日も活動できるように回復に導きます。人の自律神経には、活動時に働く交感神経と休息時に活発になる副交感神経があります。夕方になると、メラトニンというホルモンが分泌され、身体をリラックスさせる副交感神経が優位に働くようになります。脈拍、体温、血圧などが低下し、これらの変化により人は眠りへと導かれていくのです。この身体の仕組みは、一万年以上変わっていないと考えられていますが、現代社会に生きる私たちは、生活が変化して、夜遅くまで活動することが増えています。本気で睡眠不足を解消したければ、その生活習慣を見直すことが必須と言えるでしょう。
「ぐっすり眠れている人は、自律神経が正常に働き、生体リズムの調整もうまくいっている人です。決まった時間に眠くなって床に入り、朝も決まった時間に目を覚ます。規則正しいリズムで生活している人が多いのではないでしょうか?」と野本医師。睡眠不足の人の特徴に「布団に入ったらすぐに意識を失うかのように眠りに落ちる」と言うのがありますが、とくに睡眠不足でなければ、眠りに落ちるまでに通常は10〜15分くらいの時間がかかります。
レム睡眠とノンレム睡眠が交互に
睡眠には、レム睡眠とノンレム睡眠とがあります。まず眠りに入ってしばらくすると、ノンレム睡眠が現れ、浅いノンレム睡眠から深いノンレム睡眠へと移行します。身体の回復に欠かせない成長ホルモンは、最初に現れるノンレム睡眠の際に分泌されると言われています。
ノンレム睡眠が現れた後に、レム睡眠が現れます。ノンレム睡眠とレム睡眠をひとつの周期とすると、大体90分ぐらいになると言われています。あくまでも目安なので、その時間には個人差があります。その時間の差は、レム睡眠の時間に左右されるようです。
ぐっすり眠れている人は、この睡眠リズムの周期を4〜5回繰り返し、眠りが浅くなったところで目が覚めていると思われます。一方、たとえ睡眠時間はとれていても、深い睡眠のノンレム睡眠がなければ身体も脳も休まらず、眠った気がしないということになります。また、交感神経と副交感神経の切り替えがスームズであることも、よい睡眠をとれる人の特徴だと思われます。「夜になると自然と眠たくなる」、これは、身体が健康な証拠だといえるでしょう。
睡眠不足が続くと、健康にどう影響する?
生活習慣病の発症リスクが上昇
平日の睡眠不足を解消しようと思って週末に寝だめをしても、寝不足は解消されないということが、研究から明らかにされています。そして寝不足が続くと、生活習慣病や精神疾患などに大きく影響することがわかってきました。
「高血圧や糖尿病は、睡眠不足の状態が長く続くことが発症要因のひとつになっているという研究報告があります。また、うつ病や認知症の発症にも、睡眠不足が関わっていることが明らかになっています」と野本医師。

人は、昼間の活動で、身体の中に活性酸素をためています。活性酸素が増えすぎると身体の機能が衰えます。活性酸素が正常な細胞を酸化させることで、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞、がん、糖尿病など、多くの病気を引き起こす原因となります。睡眠には、こうした活性酸素を除去する働きがあります。当然、睡眠不足になると、その働きが低下するため、病気が発症しやすくなるのです。
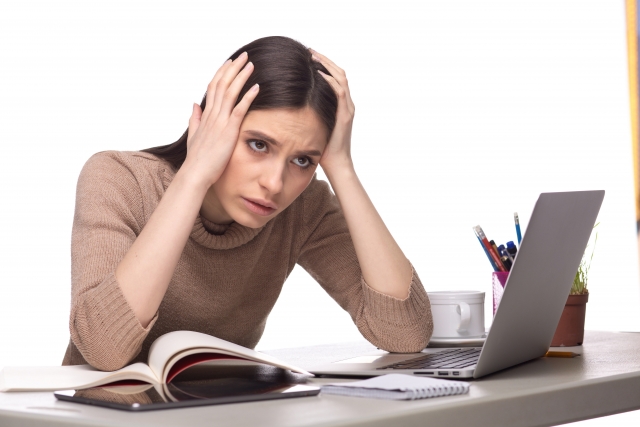
睡眠不足で、肥満やメンタルの病気にも
また、生活習慣病を引き起こす要因となる肥満も、睡眠不足に大きく関わっていることがわかっています。アメリカのスタンフォード大学の論文では、睡眠不足になると、食欲を抑える働きのレプチンと言うホルモンが減少し、逆に、食欲を増進させるホルモン、グレリンが多く分泌されるという報告があります。寝不足になると食欲が増してしまい、身体が欲するままに食べていると、当然太ってしまうというわけです。
「睡眠不足の影響で生体リズムが狂えば、自律神経にも乱れが生じるため、身体の部位に不調が現れます」と野本医師。自律神経は、体内のあらゆる臓器を動かしているため、これが乱れると、いろいろな部位に症状が現れます。動悸や息切れ、めまいが起きるなども、自律神経の乱れの影響です。野本医師によれば、メンタル系の病気も発症しやすくなるとのこと。適切な睡眠時間は、健康に生きるためには絶対に欠かせないものなのです。
最近よく聞く、睡眠負債って? その解消法とは?
睡眠負債とは、睡眠不足を借金に例え、睡眠不足の蓄積した状態のことを示しています。一日や二日の徹夜だけでは、睡眠負債とはなりませんが、毎日のように、少しずつ睡眠時間が不足していることが長く続くと、健康を阻害し、病気が発症する確率が高くなります。
寝ることだけが負債の解消に
「睡眠負債は、寝ることでしか解消できないので、今よりも少しでも多く眠るよう心がけることが大切です」と野本医師。「週末にいつもより多く眠ることは悪くありませんが、昼過ぎまで寝ていると生体リズムが狂ってしまい、夜中遅くまで眠れなくなることも。そのため、月曜の朝に起きるのがつらいということにつながります。少なくとも、午前中のうちに起きて活動する方が、心のリフレッシュにもなるでしょう」とのこと。週末の寝だめで睡眠負荷が解消されるわけではないため、日々の睡眠を増やす努力をすることを考えるべきです。いつもより早めに床につくことを試み、なかなか眠りにつけないという人は、生活習慣を見直してみましょう。
<自然に眠りにつくための心得>
●食事は就寝時間の3時間前に
寝ているときに消化活動をしなくてもいいように、なるべく眠りにつく3時間前に食事をすませます。もしも、夕飯が遅くなった場合は、なるべく胃腸の負担にならないような消化のよい食べ物を選びましょう。脂身の多い肉などは避けた方が無難です。
●食生活を見直し、栄養バランスのよい食事を
栄養に偏りがないように、朝昼晩と3食食べることが、質のよい睡眠につながります。
睡眠ホルモンと呼ばれるメラトニンは、脳内神経伝達物質であるセロトニンから生成されますが、このセロトニンは必須アミノ酸のトリプトファンから作られます。トリプトファンが豊富な、たんぱく質源をしっかり取りましょう。

●お風呂では、ぬるめのお湯につかって
体温が下るに眠くなるので、就寝の2時間前ぐらいに入浴を。寝る直前に熱いお風呂に入ると交感神経が活発になり、かえって興奮して眠りにつきにくくなります。
●部屋の照明は、暗めになるよう設定を
就寝時間が近づいたら、部屋の灯りは暗めにしましょう。室内が明るいままでは、メラトニンの分泌も進みません。リラックス出来る、暖色系の間接照明がよいでしょう。
●パソコンやスマホ画面の光を目にしない
パソコンやスマホの画面から発せられるブルーライトは、メラトニンの分泌を阻害すると言われています。就寝時間が近づいたら、こうしたデジタルデバイスには触れないように心がけましょう。
●アロマテラピーやハーブティーのリラックス効果を利用
心と身体をリラックスさせる効果のある、ラベンダーやカモミールなどの精油を利用したアロマテラピーを取り入れてもよいでしょう。同様に、寝る前にハーブティーを飲むことも、おすすめです。

●コーヒーなどカフェインの摂取を控える
カフェインには覚醒作用があるので、夕方以降は摂取を控えるべきでしょう。コーヒーの他、緑茶や紅茶にもカフェインは含まれています。また、エナジードリンクや栄養ドリンクには、多くのカフェインが含まれています。カフェインは、入眠の妨げになるだけでなく、利尿作用もあるので、夜中に眼を覚ます原因にもなりかねません。
●喫煙は、睡眠の質を悪くするので慎むべし
たばこに含まれるニコチンには覚醒作用があります。就寝前の喫煙は慎むべきでしょう。そもそも活性酸素を増やす元なので、質のよい睡眠のみならず、健康のためにもよくありません。
●メラトニンの分泌を促すために日の光を。
身体を眠りに誘うための睡眠ホルモン、メラトニンが十分に分泌されるように、朝は日の光を浴び、メラトニンの元となる、セロトニンが十分に分泌されるよう心がけます。
睡眠不足を解消するにはどうすればよい?
人間の体内時計は約25時間あり、地球の自転との間に差があります。けれども、日光を浴びることで、毎日その体内時計は調整されます。調整がうまく行われれば、決まった時間に眠くなります。脳内伝達物質のセロトニンは、体内時計を調整する働きがあると言われています。
一日中、日の当たらない屋内にいると、少しずつ起きている時間と寝ている時間がずれていって、昼夜逆転してしまうこともあります。仕事で徹夜をしたようなときも、翌日からのことを考えて、昼過ぎまで寝ているのではなく、午前中の日の光を浴びておきましょう。昼間に活発に動くと、身体が適度に疲れて寝つきがよく、ぐっすり眠れることも多いものです。
眠りにつく時間を早める努力を
睡眠不足の解消のためには、第一に、睡眠時間の確保があげられます。朝起きる時間が決まっているなら、寝る時間を早めることを考えましょう。先にあげた、<自然に眠りにつくための心得>を実行し、眠りにつく時間を早めましょう。
また、眠りにつきやすいよう、睡眠環境を整えます。枕や布団など、寝具が自分にとって心地よいかどうか、あらためて見直してみましょう。寝間着も肌に心地よくしめつけがないかなどをチェックします。湿度はだいたい50%前後、温度は季節によって適温と感じる値が違います。布団と寝間着との関係もあるので、布団に入ったときに心地よいと感じる温度を設定しましょう。
睡眠のための食事はトリプトファンの摂取を意識して
食事は、栄養バランスよく食べることが大前提です。「朝食を食べない人もいるかもしれませんが、質のよい睡眠を得るためには、きちんと取ることが大切です。体内時計を調整する働きもあるセロトニンは、必須アミノ酸であるトリプトファンから生成されます。トリプトファンは、味噌汁のだしに使う鰹や昆布、いりこなどに多く含まれています。和食で朝食を取ることもおすすめです」と野本医師。
セロトニンはメラトニンの生成にも必須なので、毎日トリプトファンの摂取を心がけましょう。また、活性酸素を増やさないことも、質のよい睡眠には重要です。抗酸化作用のある食べ物を摂取すると、細胞の酸化を防ぐことにつながります。ビタミンCやビタミンE、ポリフェノール類、ミネラル類が多く入った食材を食事に取り入れましょう。

睡眠不足が原因で、仕事や勉強中に、どうしても我慢できない程、眠くなったらどうすればよいのでしょう? 「昼食を取った後に、机に伏せて仮眠を取るのも有効です。横たわって長い時間寝てしまうと、夜に寝つけなくなったりすることもありますが、15~20分程度の短い睡眠なら、目覚めてからも眠さを引きずることがないでしょう。寝なくても、目を閉じているだけでも脳は休まります。仕事の効率も上がると思いますよ」(野本医師)

睡眠の質を高めるのも効果的
同じ睡眠時間でも、睡眠の時間帯で眠りの質は変わります。身体の疲労を回復させる働きのある成長ホルモンは、人が眠ってから夜中の3時頃までに分泌されます。寝入りばなの最初の深いノンレム睡眠時に多く分泌されるのですが、寝る時間が遅くなればなるほど、分泌量も減ってしまいます。
夜中の3時以降は、目覚めるためのホルモン、コルチゾールが分泌される為、身体は起床の準備を始めます。やらなければならないことがある場合は、夜中まで起きてダラダラと作業するよりは、早朝におきて作業した方が、作業効率がよいことを覚えておきましょう。深夜遅くまで起きていると、睡眠の質は低下します。眠る時間帯を考慮して、睡眠の質を高めましょう。
朝起きたときに、眠った気がしないというのは、寝ている間に身体が休まっていないことのあらわれです。もしかしたら、消化に時間がかかる食べ物のせいで、胃腸が休まらなかったことが影響しているかもしれません。また、いびきをかいていたとすれば、睡眠時無呼吸症候群の可能性もあります。鼻づまりがひどく、そのせいで睡眠が阻害されているかもしれません。寝具が身体に合っていないということもあるでしょう。
眠れないからといって、寝る前にお酒を飲むと、利尿作用のせいで目覚めたり、睡眠の質が落ちたりします。原因がどこにあるのか探してそれを解消すれば、睡眠の質を高められます。
長期にわたる睡眠不足は、確実に身体への負担となり、病気のリスクを高めます。人生100年時代に突入しています。健康で充実した人生を送るためにも、生活習慣を見直して、適切な睡眠時間を確保しましょう。
取材・文/仲尾匡代
関連するキーワード

ナチュラルクリニック代々木 院長
野本裕子(のもとゆうこ)
埼玉県生まれ。信州大学医学部卒業。<NPO法人>予防医学・代替医療振興協会理事、<一般社団法人>認知症予防・改善医療団理事。東京医科歯科大学にて臨床研修後、予防医療、美容医療に携わる。平成28年より現職。薬に頼らず、日常の食生活の改善とサプリメントを中心とした「細胞膜強化栄養療法」での治療を長年行っている。著書に『医師もびっくり! 認知症が治っている』(素朴社刊)
ナチュラルクリニック代々木 Webサイト:http://www.natural-c.com
※記事内の写真・文章・価格・人物などは記事の更新日時点での情報となります。
現在の情報と異なる場合もございますので、ご了承ください。
大塚家具のLINE公式アカウント!
続けて読みたい!あなたにオススメの記事




















