睡眠負債を解消して、「ぐっすり」を手に入れよう!

2017年のユーキャン新語・流行語大賞にベストテン入りした「睡眠負債」。忙しい日本人は、睡眠負債を抱える人が少なくありません。そこで、睡眠負債の基礎知識と、上手に解消するポイントを、脳科学者で睡眠研究の第一人者でもある早稲田大学・枝川義邦教授に解説していただきました。
仕事上のミス、風邪、認知症、がんなどを誘発
──「睡眠負債」とは、どのような状態を指すのですか?
本人も気づかないくらいのわずかな睡眠不足であっても、蓄積されると心と身体に悪影響を及ぼす可能性が大きくなってしまう状態です。
──「知らないうちに、眠りの借金が膨れあがっていた!」という状況を、「負債」という言葉がよく表しています。どのような弊害が出やすいでしょうか?
脳がうまく働かなくなるので、仕事上でミスが増える、判断力が低下する、もの忘れが多くなる、怒りっぽくなるといった症状が出やすくなります。免疫機能が落ちるので風邪を引きやすくなるほか、長期的に睡眠負債が続けば、肥満、高血圧症、糖尿病、認知症、がんなどにかかるリスクも高くなります。
子どもから大人まで4割以上が睡眠負債に
──日本人でどれくらいの割合の人が睡眠負債を抱えていますか?
厚生労働省が行った調査では、20歳以上の男女約4割の平均睡眠時間が6時間未満という結果になりました。ただし、最近は子どもたちの睡眠時間も減っていることが指摘されています。子どもたちは、自分でつくる生活サイクルだけでなく、大人の影響も受けやすいことから、睡眠負債を抱えてしまいがちなのです。
──子どもにまで及んでいるのは問題です。睡眠負債に陥らないために、適切な睡眠時間は?
個人差はありますが、一般的に6時間半〜7時間半と言われています。平均して7時間くらいを意識するとよいでしょう。子どもの場合には、もっと長い睡眠時間が必要とも言われていますので、年齢帯に合った時間を知っておくことが必要です。
──睡眠負債になる原因は、どのようなことにありますか?
近年、働き方改革が進んでいますが、それでもまだ日本人の中に「勤勉が美徳」という意識が強く、“働きすぎ”の印象がぬぐえません。都市部では終電が遅いので、残業も遅くまでできてしまいます。その他、24時間営業の飲食店やコンビニなどが多く、夜になっても明るい環境や、スマートフォンやパソコンなどを夜遅くまで楽しんで睡眠をおろそかにしてしまう生活習慣など、多くの原因があります。

睡眠負債をキャッチする3つのサイン
──自分が睡眠負債を抱えていることを、いち早くキャッチするサインは?
次に挙げた3つのうち、どれか1つでも当てはまっていたら睡眠負債の可能性が高いと言えます。
1.朝起きたとき、スッキリ目覚めない
充分な睡眠時間が足りていない可能性が高く、朝起きたときに頭がボーッとしてしまいます。起きるタイミングの影響もあるので、気持ちよく起きられるようにするのが1日を気持ちよく過ごせる秘訣です。
2.午前中に眠くなってしまう
私たちは、起きてから3〜4時間後に脳の働きが活発になります。たとえば、7時に起きれば11時ごろに活発になるはずですが、そのころに眠気を感じているようであれば、睡眠負債かもしれません。
3.夜、布団に入ったらすぐに寝落ちする
夜に布団に入ったら、10〜15分ほど、まどろみながらだんだん眠くなって入眠するというのが自然な寝入り方です。すぐに寝落ちするのは、睡眠がすぐにでも必要であった可能性が高いので要注意です。
夜の睡眠の準備は、朝から始まっている!
──「睡眠負債かも知れない」と思ったとき、解消するポイントを教えてください。
睡眠時間を充分にキープすることの他に、睡眠の質を高めることも重要です。夜の過ごし方にばかり目を向けがちですが、朝からの1日全体を見渡す視点で生活を見直してみてください。
朝は、起きたら部屋のカーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。眠気ホルモンであるメラトニンの分泌が抑えられます。光を浴びることは、14~16時間後にメラトニンが分泌されるスイッチを入れることにもなり、夜間の眠気をスムーズに運んでくれます。大豆製品や動物性たんぱく質を含んだ朝食をとれば、身体を目覚めさせるのと同時に体内でメラトニンが産生されてリズムも整います。
昼はなるべく活動的に過ごし、ランチ後に眠くなったら15~20分程度の仮眠で脳をリフレッシュさせることが有効です。日中と夜間とのメリハリをつけることを意識しましょう。
夕方以降は、徐々に睡眠のための準備を進めます。入浴はぬるめのお湯に浸かり、身体の中心部の体温をいったん上げると、下がるときに自然な眠気が訪れます。ベッドに入る前や入ってからは、スマートフォンなどをいじってブルーライトの強い光を浴びないように気をつけて。メラトニンの分泌を妨げてしまいます。

──朝から始まる一日の生活全体に目を向けるのですね。その他に、気をつけることはありますか?
寝具にもぜひ気を配ってください。寝具は眠っているときに身体を包んでいるものです。直接肌に触れるうえ、身体を支える役目もあるので、寝心地が左右されるアイテムです。寝具選びを間違えると、生活リズムを整えても睡眠の質を上げることはできません。
寝返りを妨げないマットレスを
──どのような寝具がおすすめですか?
マットレスは、身体をしっかり支えて寝返りを妨げない高反発素材がおすすめです。最近では、高反発と低反発をミックスして弾力性と柔らかさを両立させるなど、さまざまなタイプがあります。自分に合った、寝心地のよいマットレスを選びましょう。アドバイザーの方に相談するのも良いですね。
また、布団の中で寝ているときに理想的な寝床内環境は、温度33℃・湿度50%と言われています。それを実現させてくれるのが羽毛布団です。雲のように軽いのも身体に負担がかからず魅力だと思います。
寝るときの服装は部屋着やジャージなどの人もいますが、汗でジメジメしていると快眠できないので、パジャマを着ることをおすすめします。汗を吸い取り発散させる効果もあるので最適です。
──ぐっすり眠れる寝室づくりでアドバイスは?
リラックスして過ごせるように、暖色系の間接照明を取り入れるのが効果的。窓の外からの光が強ければ、遮光カーテンなども活用してください。眠るための環境づくりは、五感を意識して整えることも必要です。睡眠作用の高いアロマを炊いたり、リラックスできる音楽をかけたりするのもいいですね。
癒やし効果の高いピンクノイズ音楽
──どのような音楽がおすすめですか?
最近は、「ピンクノイズ」という音が注目されていて、睡眠の質の向上や、癒やし効果が高いことが知られています。私が監修したCD『睡眠時に適した~レガリア・リラクシング・ミュージック』でも体験できるので、ぜひ聴いてみてください。
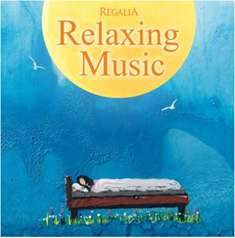
詳細はこちら
https://www.idc-otsuka.jp/item/item2.php?id=other93970
──最後に、読者へメッセージをお願いします。
起きている時間と眠っている時間は、表裏一体の関係。両者に目を向けて、1日24時間全体が睡眠に影響している意識を持つことが大切です。特に睡眠中は「単に意識が遠ざかっている状態」と思っていると、おざなりにされがちです。1日の約1/3の時間を費やしているのですから、寝具や寝室環境を見直して質のよい睡眠につなげてください。起きている時間と同様に眠っている時間も丁寧に過ごすことができれば、心と身体が良好に変わっていくはずです。
取材・文/内藤綾子
関連するキーワード

脳科学者/早稲田大学教授
枝川義邦(えだがわよしくに)
東京大学大学院薬学系研究科博士課程を修了して薬学の博士号、早稲田大学ビジネススクールを修了してMBA を取得。脳の仕組みや働き、人間のこころや行動について、テレビや雑誌への出演も多い。2015 年度に早稲田大学ティーチングアワード総長賞、2017年度にユーキャン新語・流行語大賞を受賞。著書:『 「脳が若い人」と「脳が老ける人」の習慣』(明日香書店)『「覚えられる」が習慣になる!記憶力ドリル』(総合法令出版社)監修:『ぐっすり眠れる睡眠の本』(宝島社)『 たった30 日!もの忘れストップ!大人の記憶脳ドリル』(学研)など。
※記事内の写真・文章・価格・人物などは記事の更新日時点での情報となります。
現在の情報と異なる場合もございますので、ご了承ください。
大塚家具のLINE公式アカウント!
続けて読みたい!あなたにオススメの記事





















