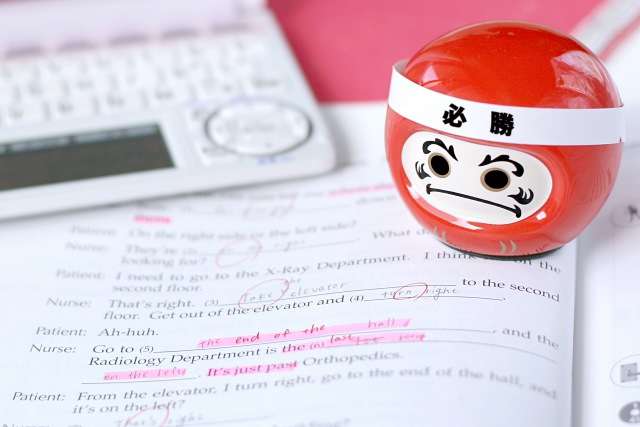夜勤のあるシフト勤務。睡眠の質を上げるには?

タクシーやトラックなどの職業ドライバーの方々の中には、深夜乗務のある人たちがいます。神経の集中が必須となる車の運転は、寝不足状態のままだと大変危険です。また、入院設備のある病院勤務の医療従事者にも夜間勤務はつきものです。寝不足による注意散漫が許されない職務であり、夜勤前後、および夜勤中の仮眠などでは、効率よく、質のよい睡眠をとる必要があります。
他にも、深夜まで稼働している工場や、店舗などで夜中に勤務する人たちは、昼間、どのようにして睡眠をとれば、身体の疲れが回復できるのでしょう? 一般社団法人睡眠スパ協会代表理事、睡眠健康指導士の金沢優治さんに、お話を伺いました。
夜勤明け、質のよい睡眠をとるには?
金沢さん「業界的には人手不足のため難しいとは思いますが、まずは交代勤務のシフトを見直す必要がありますね。早いサイクルの交代勤務では慢性的な眠気に襲われます。日勤、準夜勤、夜勤を2日適度で交代勤務するよりも、1週間で交代するような回転シフトの方が生体リズムを崩しにくくしてくれます」
その上で、個人で出来る対策として、下記の5つの点を心がけるとよいとのこと。
夜勤に出向く前と、夜勤から帰ってきてからの睡眠についてアドバイスをいただきました。
<夜勤明けの睡眠 心がけたい5つのポイント>
1.夜勤前に、1〜2時間の仮眠をとる
勤務中に眠くなるのを少しでも減らすことが出来るうえ、夜にとるべき睡眠を前倒しでとるという意味合いもあります。
2.高カロリーな食事やカフェイン類を避ける
カロリーの高いものは、消化に時間がかかるものが多く、睡眠中に胃腸が活発に動いていると、睡眠の質を下げてしまいます。また、カフェインは覚醒作用があるため、寝つきが悪くなったり、寝ても目が覚めてしまったりします。
3.夜勤明けで帰宅する際は、日光を浴びない
日光にあたると、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌がストップし、覚醒スイッチが入ってしまうので、サングラスをして肌も露出せずに帰りましょう。
4.昼部屋を完全に暗くして光を遮断し、騒音を減らす空間にする
明るいと身体が自然に目覚めてしまうので、昼間でも真っ暗な部屋で寝るのが理想的。耳栓を使っても違和感なく寝られる人は、使用した方がよいでしょう。

5.寝室を、完全にリラックス空間にする
温度は26℃前後の暑くも寒くもない程度に。副交感神経を優位にして眠りにつきやすいようにするために、音楽をかけるよりはアロマを使用するなど、香りでリラックス効果を高めた方がよいでしょう。
夜勤中の仮眠。 短い睡眠を質のよいものにするコツとは?
「夜勤中に仮眠をとれる時間にもよりますが、30分程度の短時間の場合であれば、午前1時〜3時の間での仮眠をお勧めします」と金沢さん。この時間帯が、生体リズムにおいて、最も睡眠を必要とする時間帯であり、眠くなる時間でもあります。短い時間での効率のよい仮眠のポイントとしては、完全に横になって寝るのではなく、リクライニングのある椅子やソファーなどに座ったり、机にうつ伏せになったりして目をつぶります。

目を覚ました後は、ストレッチや10回程度のスクワットなど身体を動かして明るい場所でコーヒーなどのカフェインをとります。夜勤中に食べると、消化活動にエネルギーが使われ、眠くなってしまうので要注意。仮眠にもう少しの時間がとれるのであれば、自分の睡眠周期を1〜2回程度眠るとよいでしょう。
一般的には、90分周期の人が多いと言われていますが、最近ではスマートフォンのアプリなどを使って自分の睡眠周期を調べることも出来ます。
「例として、90分周期の人であれば、それが2回で3時間とれるのが理想です」(金沢さん)。その際は、しっかり横になって布団をかぶって眠ります。このとき、布団をかぶりすぎるのはよくないとのこと。寝返りがうてるぐらい、上布団は2枚ぐらいにしておくとよいでしょう。
夜勤がある日の心がけとは?
「セロトニン生成のために、バランスのよい食事を心がけましょう。そして、日中に日光を浴びることを忘れないでください」と金沢さん。朝食も昼食も抜くことなくしっかり食べ、夜勤に入る前には、消化のよいメニューで夕食をとります。

セロトニンとは、たんぱく質の必須アミノ酸であるトリプトファンと、目から入る日光により生産される脳内物質で、主に生体リズムや生理機能を調節し、精神を安定させると言われています。夜になると、このセロトニンがメラトニンに変化し、眠りをもたらします。
セロトニンの生成のためには良質なたんぱく質が必要ですが、夜勤前に動物性たんぱく質を多く取ると消化に時間がかかり、眠くなったり、仮眠の際に深い眠りを得られなかったりするので、要注意です。
「夜勤業務は生体リズムを崩しやすいということを踏まえ、夜勤と昼勤、休日のペースをなるべく一定にすることが大切です。昼夜逆転している人は昼前に起床し、日が出ている時になるべく活動するといった生活習慣を整える事を意識してほしいですね」と金沢さん。
基本的に、夜中に睡眠がとれないと、身体への負担が大きくなるのですが、あまり気に病みすぎても精神的に好ましくありません。人間の生体リズムを変えることは出来ないので、仮眠だったり、昼間の睡眠だったりと、眠れるときに少しでも質のよい睡眠になるよう、普段から心がけることが大切です。日中に日の光を浴びることや、正しい食生活が、質のよい眠りにつながることを忘れないようにしましょう。
取材・文/仲尾匡代
取材協力/一般社団法人睡眠スパ協会
PSC 〜Pleasant Sleep Club〜
http://psc-sleep.jp/index.html
関連するキーワード

一般社団法人睡眠スパ協会 代表理事 PSC~Pleasant Sleep Club~ 代表
金沢優治(かなざわゆうじ)
自身の睡眠障害を自分の力で克服し、その後、睡眠健康指導士の資格を取得。経験を生かして一般社団法人睡眠スパ協会を設立。独自の睡眠スパ(熟睡マッサージ)を開発し、カウンセリングと合わせたメニューを提供。個人や店舗、企業などを対象に、睡眠コンサルタント、セミナー講師などの業務でも活動中。
大塚家具のLINE公式アカウント!
続けて読みたい!あなたにオススメの記事