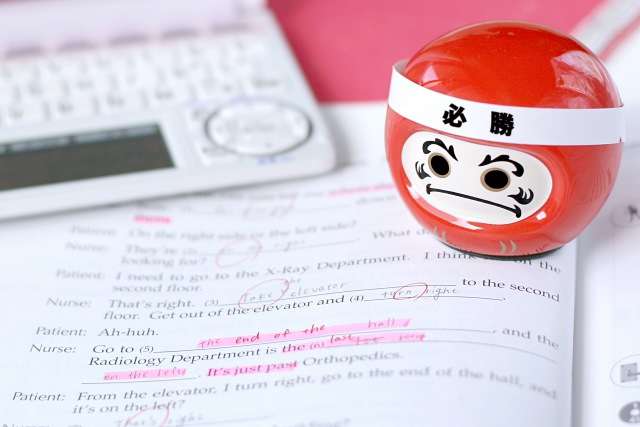人にはなぜ睡眠が必要? 睡眠の仕組みとは

人はなぜ眠りを必要とするのでしょうか。現在、睡眠については、さまざまな角度から研究が行われているそうです。睡眠時間が極端に短い場合、毎日の睡眠が不規則な場合、身体にはどのような影響があるのか。科学的な研究によって推察された、人にとっての睡眠について、江戸川大学社会学部人間心理学科准教授の山本隆一郎先生にお話を伺いました。
人にはなぜ睡眠が必要?
睡眠はなぜ必要なのか。これは、なぜ人は生きるのか、という問いと同様に答えが難しいものです。科学的な知見というのは「どのように、どういうメカニズムで?(How)」には答えてくれますが、「なぜ?(Why)」に答えてくれるわけではありません。さまざまな研究結果や見解、考察を踏まえ、どのようなメカニズムで人が毎日眠るのか、ということについてお伝えします。
人だけでなく、ほとんどの哺乳類の動物は、“なぜか”一日中活動を続けることはなく、一日の中で覚醒と睡眠を繰り返すことがわかっています。人の場合は、昼に活動して夜眠る、「睡眠—覚醒パターン」がありますが、多くの哺乳類の野生動物は、昼間に眠り夜間に活動をします。
野生動物の場合には、捕食動物に見つかる危険性がある時間に眠り、疲れを回復させ、活動の準備状態を作ることで生存の可能性が高まるために夜行性になったと考えられます。言い換えるならば、選択圧(生存率に影響を与える自然環境の影響)により毎日眠るということが獲得されたと考えられてきました。
しかしながら、人は文化を形成し安全を確保しているのにも関わらず、“なぜか”睡眠—覚醒のパターンを持っています。つまり、自然環境の影響により睡眠—覚醒パターンが形成されているわけでは無く、一日の中でいつ覚醒して、いつ睡眠をとるか?を決める仕組みが備わっており、その周期は種によって異なると考えられます。
人の睡眠—覚醒パターンは、脳の視交叉上核(しこうさじょうかく)の働きにより形成されているとされています。視交叉上核は、さまざまなホルモンや自律神経活動の日内変動を調整しており、いわば身体の中の時計のような働きをしていることから、体内時計とも呼ばれています。なお、視交叉上核の働きによって、睡眠—覚醒の周期だけではなく、食事や飲水行動、体温などさまざまな活動の規則性が作られています。
身体と脳にとっての睡眠
睡眠は積極的な心身の健康づくりの時間
──人にとって、身体や脳への睡眠の必要性を教えてください。
起きている間、人は常に環境からの情報を処理し、身体を使って環境に働きかけています。そのため、覚醒状態が続くと、頭も身体もたくさんのエネルギーを使うことになります。睡眠には、疲れた頭や身体を休める働きがあります。また、睡眠にはノンレム睡眠とレム睡眠があります。これらは、人体にとってそれぞれ次のような役割を果たしています。
<脳を休めるノンレム睡眠>
睡眠の前半に出てくるノンレム睡眠中には、脳の活動が緩やかになるとともに、手足の末梢の皮膚温が高まり、熱放散が起こることで深部体温が低下します。これにより日中にエネルギーを使ってヒートアップした脳をクールダウンさせます。このことから、ノンレム睡眠は脳を休める睡眠であると考えられています。
<身体を休めるレム睡眠>
睡眠の後半に多く出るレム睡眠中には、脳の活動は比較的活発でも、筋肉が弛緩し、起きている間に常に緊張している抗重力筋(地球の重力に対し姿勢やバランスを保つために動く筋肉)も弛緩します。このことからレム睡眠は身体を休める睡眠であると考えられています。
そして近年では、睡眠には人の脳や身体を休める以上にさまざまな意義があることがわかってきています。例えば、レム睡眠や、脳の活動が緩やかなノンレム睡眠には、記憶の定着や整理する働きがあるとわかってきました。また、ノンレム睡眠中には脳の老廃物(アルツハイマー型認知症のリスク因子)を排出する機能があることもわかっています。
さらに、睡眠は脳のなかでも、とくに実行機能(注意を向けたり切り替えたり、文脈に合った判断をする機能に関する部位)の発達を支えていることもわかっています。睡眠は、疲れた心身を休める時間であるだけでなく、積極的な心身の健康づくりの時間であると言えるでしょう。
人の精神面にとっても重要な睡眠
──睡眠が人の精神面へ与える影響や必要性を教えてください。
睡眠中は、脳や身体の休息、心身の健康づくりだけでなく、人の精神機能の調整も行われています。睡眠中は身体の恒常性(環境の変化に関わらず身体の内部状態を一定に保とうとすること)に関わる神経・免疫・ホルモンといった整理機能の調整が行われています。こうした身体の情報系は、精神的な機能とも大きく関わっています。
これは、女性の月経を例にとるとわかりやすいかと思います。月経周期と気分変動が関わっていることは、女性は体験的に理解しやすいと思いますが、睡眠が乱れると月経周期の乱れにつながり、気分も不安定になりやすくなります。このように、睡眠に問題があると、神経・免疫・ホルモンの機能の問題につながり、精神・行動上にも悪影響があります。
また、最近の大脳生理学研究では、不眠状態が続くと不安などの負の感情を抑えることが困難になることが報告されています。睡眠は、日々を穏やかな気持ちで過ごすこと、望ましい判断をする上での土台になると言えるでしょう。
眠ることの恩恵を受けるために
──「よい睡眠」の条件とは?
「よい睡眠」とは何かを定義することは非常に難しく、睡眠を専門とする研究者間でも強調する観点や、何にとってよいとするかによっても回答は異なると思います。私が一般的な心身の健康にとってよい睡眠を説明する際には下記の3点を挙げています。
●十分な睡眠時間を確保していること
まず条件として挙げられるのが、睡眠の量に関する観点です。人間の場合、必要な睡眠時間は年齢によって異なり、成人はおおむね7時間程度が必要とされています。各年代における健康のために推奨される睡眠時間である「推奨睡眠時間」と、推奨時間よりは短いか長いけれども、範囲内に収まっていれば許容できるという「許容睡眠時間」を示します。
もちろん、必要な睡眠時間には個人差がありますがご自身の年齢からよい睡眠の量の目安とするとよいでしょう。
表:米国睡眠財団の提唱した推奨睡眠時間
| 年齢 | 推奨睡眠時間 | 許容睡眠時間 |
| 0-3ヶ月 | 14-17時間 | 11-19時間 |
| 4-11ヶ月 | 12-15時間 | 10-18時間 |
| 1-2歳 | 11-14時間 | 9-16時間 |
| 3-5歳 | 10-13時間 | 9-14時間 |
| 6-13歳 | 9-11時間 | 7-12時間 |
| 14-17歳 | 8-10時間 | 7-11時間 |
| 18-25歳 | 7-9時間 | 6-11時間 |
| 26-64歳 | 7-9時間 | 6-10時間 |
| 65歳以上 | 7-9時間 | 5-9時間 |
●毎日規則正しく1回の睡眠をとっていること(幼児以降)
次に挙げられるのが、睡眠の規則性に関する観点です。生まれたばかりの赤ちゃんは、睡眠—覚醒リズムが確立していないため、一般的に昼間も睡眠をとりますが、4歳にもなると、昼間の睡眠や覚醒を維持するための昼寝はほぼ必要なくなり、夜間に一度だけ眠るようになります。
睡眠—覚醒リズムの確立以降は、体内時計にとっての夜に眠ることが大切です。
例えば、時差ボケのような強制的に不規則になることを想像してみるとわかりやすいでしょう。時差ボケ状態では、体内時計の夜が現地時間の朝であったりすると、現地の朝が眠かったり、夜がなかなか眠れなかったりします。海外に行かなくても、週末にお昼まで寝てしまう生活や、昼寝をしたために夜眠れないといった生活により不規則な就寝—覚醒習慣をしていると、睡眠の恩恵が受けられません。
近年、こうした生活による不規則な睡眠—覚醒習慣による問題は、「社会的時差ボケ」と呼ばれ注目されています。
●睡眠が妨害されていないこと
最後に挙げられるのは、睡眠の質の観点です。睡眠の質という言葉は一般的によく使われますが、何をもって質がよいとするか。そもそも、質を定義できるかは、研究者間でも見解が異なります。私がお伝えする睡眠の質とは、睡眠の開始が容易で、途中で睡眠が妨害されていないことを指します。
規則正しく、自分に合った睡眠時間をとれるようにしていても、騒音や光などの外的な刺激、睡眠時無呼吸症候群といった身体的な問題、仕事のストレスのような心理的な問題などがあると、ぐっすり眠ることができません。睡眠に影響する基礎疾患があるのであれば、しっかりと治療し心地よい環境で眠ることが重要です。
山本先生に訊いた、「眠ること」の捉え方
──そもそも人はなぜ眠る必要があるのでしょうか。山本先生のご経験から感じられることを教えてください。
多くの方は、なぜ覚醒が必要なのかという質問はしません。なぜなら、覚醒時には意識があり、「まさに」生きている時間と実感しているからです。一方、睡眠は一時的に意識がなくなっている時間で非常に消極的な時間であると考え、なぜ必要? 短い眠りで済む方法はないか? という問いが出るのだと思います。
睡眠はただ頭や身体を休める時間ではなく、心身の健康や覚醒の質を支える「活動的な時間」だと思います。人も動物も、覚醒と睡眠という2つの活動を切り替えて積極的に生きていると言えます。と考えると覚醒の必要性と同様に、睡眠の必要性にも疑問がなくなるような気がします。
──睡眠の悩みは、どのように捉えることができるでしょうか?
睡眠の悩みは、睡眠時間を確保できる生活ができていない、一時的な睡眠不足を補うために生活習慣が乱れていることによるものも少なくありません。もしかすると、睡眠の悩みは、日頃の生活のあり方や、お仕事との向き合い方を振り返る、いいきっかけを与えてくれるのかもしれません。そう思うと、睡眠の悩みから大事なことを学べるかもしれません。
また、睡眠を改善することに焦る必要はありません。焦ると「眠らなきゃ!」と頑張りすぎて、かえって不眠になってしまったり、変な時間に睡眠を補おうとしてリズムが乱れたりします。規則正しく同じ時間に睡眠を確保する生活を続けようと、日々の暮らしを見直してみることが大切です。そうすれば、多くの睡眠のお悩みは改善するのではないかと思います。
しかしながら、睡眠の悩みの背景に、何かの病気や睡眠障害が潜んでいる場合も少なからずあります。生活習慣を工夫しても睡眠の問題が続いていて、生活に支障がある場合には、かかりつけの医師に相談をするほか、睡眠専門の医師に相談するようにしましょう。
いかがでしたでしょうか?睡眠は身体や心の休息のみならず「積極的な心身の健康づくりの時間」という言葉がとても心に残りました。眠る時間を活動的と捉えることは、睡眠の悩みを持つ方、忙しい日々を過ごす方々にとって、睡眠に対する視野が広がり、よりよい睡眠への取り組みの一助となってくれるかもしれません。
取材・文/数野由香子
関連するキーワード

江戸川大学社会学部人間心理学科准教授
山本隆一郎(やまもとりゅういちろう)
江戸川大学社会学部人間心理学科准教授。江戸川大学心理相談センターセンター教員。これまで、研究や教育活動と並行し、心療内科や心療内科併設の私設カウンセリングルームにて臨床心理相談を担当。現在の専門分野は、臨床心理学(認知行動療法)・睡眠行動医学・睡眠公衆衛生学。
http://www1.edogawa-u.ac.jp/~yamamoto/index.html
※記事内の写真・文章・価格・人物などは記事の更新日時点での情報となります。
現在の情報と異なる場合もございますので、ご了承ください。
大塚家具のLINE公式アカウント!
続けて読みたい!あなたにオススメの記事