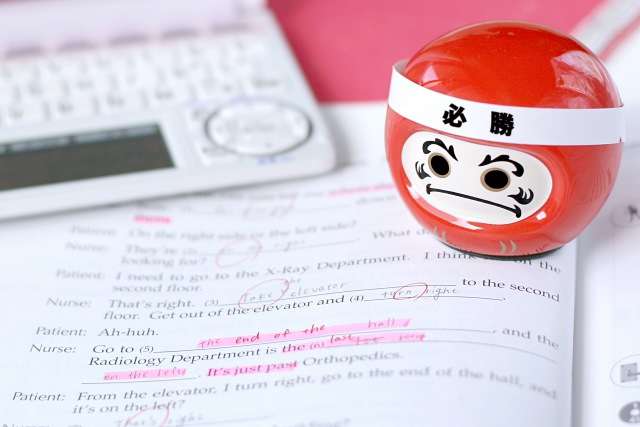ツボと呼吸法で安眠を手に入れよう ~東洋医学から学ぶ~

眠りたいのになかなか寝つけない、睡眠時間をしっかり確保しているのに寝た気がしない。そんな悩みはありませんか?一方で、眠れないからといって薬に頼るのも抵抗を感じる…という方も多いのではないでしょうか。そんな時は東洋医学である呼吸法やツボの力を借りてみるのもよいかもしれません。
今回は東洋医学から安眠を手に入れる方法を東洋鍼灸専門学校校長である竹内廣尚先生に伺いました。
東洋医学とは
東洋医学とはアジア一帯で発生した伝統医学の総称で、その歴史は約三千年にも及びます。病気を検査で判断し、その原因や異常部位を集中的に治療するという西洋医学とは異なり、東洋医学は、人の心と身体の不調や症状を診察し、診断結果に基づき人が本来もつ治癒力を生かしながら不調や病の改善を促します。
治療法が科学的理論によって構築される西洋医学に対し、東洋医学では漢方薬やツボへの鍼灸治療が中心で伝統や経験により構築されます。「実際に経験したからこそ、自信を持って教えることができる」と竹内先生は言います。
東洋医学で考える眠れない理由

東洋医学には「気」という考え方があります。気とは自然界にあふれているエネルギーのようなものとされ、人の体内にも臓器から指先まで巡っているとされています。この気が巡っている道筋を「経絡(けいらく)」と呼びます。また、東洋医学では24時間を干支で区切り、各経絡が活発に動く時間が決まっているとされています。そして睡眠時間帯に関わる経絡に何らかの不調があると睡眠に影響が出ると考えられています。
| 干支 | 時間 | 経絡 |
| 子 | 23:00~1:00 | 肝経 |
| 丑 | 1:00~3:00 | 肺経 |
| 寅 | 3:00~5:00 | 肺経 |
| 卯 | 5:00~7:00 | 大腸経 |
| 辰 | 7:00~9:00 | 胃経 |
| 巳 | 9:00~11:00 | 脾経 |
| 午 | 11:00~13:00 | 心経 |
| 羊 | 13:00~15:00 | 小腸経 |
| 猿 | 15:00~17:00 | 膀胱経 |
| 酉 | 17:00~19:00 | 腎経 |
| 戌 | 19:00~21:00 | 心包経 |
| 亥 | 21:00~23:00 | 三焦経 |
その中でも睡眠にもっとも関わりがあるのが23時〜1時の胆経(胆のう)と、1時〜3時の肝経(肝臓)です。この肝経や胆経が疲労または興奮していると、眠りを妨げる原因になってしまうそう。安眠のためにも過度な飲酒や寝る直前の食事、油っこい食事は胆経や肝経を刺激するため、注意しましょう。
東洋医学で安眠を手に入れる方法
~呼吸法とツボへの鍼灸治療~
では、安眠のためにはどうすればよいのでしょうか。今回は自分でできる呼吸法と鍼灸院で治療できるツボについて伺いました。
白隠禅師(はくいんぜんじ)の呼吸法
1.リラックスして仰向けに寝る。
2.片方の中指の指先をへそと恥骨結合の真ん中にある丹田(たんでん)にあてる。
3.息を吐いたら、男性はお腹いっぱいに、女性は胸いっぱいに息を吸い込み、指をあてている丹田を押し上げ、息を吐く。
【呼吸時のイメージ方法】
何度か呼吸を繰り返したら、息を吸うときと吐くときの流れを意識してみましょう。
息は以下の順に手や脚に流していきます。各部位に息を流すということにピンとこない方は、手や脚の中に土管のように穴があいていて、そこへ空気を送り込むようなイメージをしてみてください。背中は背骨の中を順に息が流れていくというイメージをするとよいそうです。
1呼吸目:
息を吸うときは、手の指先→前腕→上腕→肩→頚→頭→顔→咽喉→胸部→上腹部→丹田の順に流れて丹田を膨らませます。
息を吐く時は、下腹部→大腿部→下腿部→足裏の順に流れて足裏から息を吐いていきます。
2呼吸目:
息を足裏から吸い、足裏→下腿部→大腿部→お尻→腰→背骨を上り→肩→上腕→前腕→手のひら→指先に流れ、指先から息を吐きます。
この呼吸の流れを繰り返すか、やりやすい流れで新たにルートを作っても構いませんが、丹田は必ず膨らませることがポイントです。
鍼灸院で治療できる安眠のツボ3選
東洋医学では、人体を巡る気の流れとされる経絡と神経が集まるポイントにあるものを「経穴(けいけつ)」と言います。これがツボにあたります。以下に安眠に効果的なツボをご紹介します。
裏失眠(うらしつみん)
かかとの裏側にあるツボで、高ぶった神経を落ち着かせ安眠に導きます。ここに熱さを感じるまでお灸をしてみましょう。頭が緊張していることが多いため、まず頭に散鍼*(さんしん)をしてからお灸をすると、さらに効果的だそう。
*散鍼とは鍼治療の1つでツボにこだわらず、圧迫によって痛みを感じる部位や凝り固まっている部位にそれぞれの深さで鍼を抜き差しすること
天柱(てんちゅう)、風池(ふうち)、完骨(かんこつ)
天柱:襟足の首の骨から指1本分左右に開いたところにあるツボ。自律神経を整える働きがあります。
風池:天柱から指1本分左右に開いたところにあるツボ。血流改善、肩こりをほぐす働きがあります。
完骨:風池からさらに指1本分左右に開いたところにあるツボ。肩こりをほぐす働きがあります。
これらのツボに指を引っ掛けて、ゆっくりと上方向に牽引します。これを揺らしたりはせず、3〜5分かけて行いましょう。
巨闕兪(こけつゆ)
肩甲骨の間にあるツボ。心を鎮め、安眠に効果があります。ここに5分間、鍼を置いてみましょう。
いかがでしたでしょうか?安眠に効果的な呼吸法とツボを教えていただきましたが、眠れない原因は1つではなく、さまざまなメカニズムで発症すると考えられています。そのため、どのようなメカニズムで発症したのかを東洋医学的に判断した上で、ツボに適切な手技で鍼灸を行わないと症状は改善しません。
まずは専門家に、どのようなメカニズムで眠れなくなっているのかを診てもらいましょう。
文/今井菜穂子
監修:東洋鍼灸専門学校 校長 竹内廣尚(たけうち ひろなお)先生
古典の文献を紐解くと共に、鍼灸の科学化を推し進め、研究し、治療法の充実化を目指す。臨床経験豊富な講師の先生方や教育熱心な専任の先生方、また本校卒業生の協力を集結して、学生を指導。「独立開業を目指す、プロフェッショナルな鍼灸師」の育成を行っています。