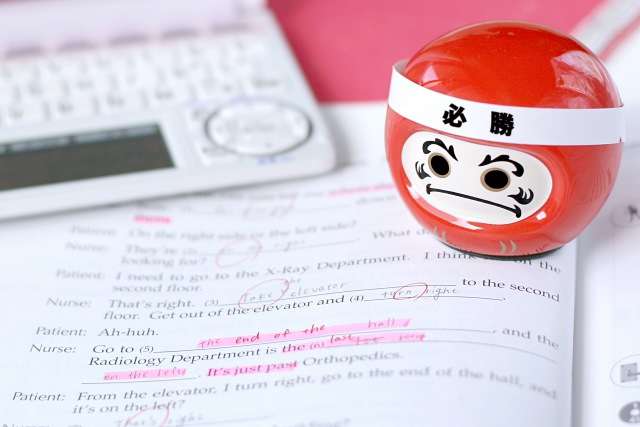光で体内時計を調節して睡眠リズムを整えよう!

ワクワクしている時や、落ち込んでしまった時など、就寝時間にベッドに入ったのになかなか寝つけないという経験をされたことはありませんか?眠れない夜が長期間続くと、疲れが溜まるだけでなく体調を崩してしまう原因につながることも。
そんな眠りのリズムを乱してしまう原因の1つとして考えられるのが『体内時計のずれ』です。乱れてしまった体内時計を調整して睡眠のリズムを整える方法を筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構 副機構長 櫻井武教授に伺いました。
睡眠不足が身体に与える影響は?
睡眠は身体を休めるだけでなく、脳の休息やメンテナンス、記憶の整理などの役割もあります。睡眠不足の翌日、思うように頭が働かないと感じたことがある方も多いと思いますが、徹夜をした翌日はお酒に酔ったときと同じくらい注意力が低下すると言われています。
さらに、長期的な睡眠不足が続くと、生活習慣病やがんなどのさまざまな病気にかかるリスクが上がるという研究結果も出ています。
仕事や勉強など、忙しい日々を送る現代人はついつい睡眠を後回しにしがちですが、『眠くなったら寝る』という身体が発するサインに素直に従って行動することが大切です。
睡眠不足と体内時計のずれ
一方で、夜になかなか寝つけないという悩みを抱えている方もいるかと思います。眠りたいのに眠れないというのは、さまざまな原因が考えられますが、多忙で不規則な生活をしている方は『体内時計のずれ』が原因の可能性も。
体内時計とは、「朝起きて日中は活動し夜になったら眠る」という、地球の自転周期(24時間)に合わせた生活リズムを作るものです。日々の睡眠の周期に合わせて適切な時間に眠気を感じるなど、生物に生まれつき備わっている機能です。睡眠と覚醒のリズムが乱れ体内時計がずれることで、寝つきが悪くなり、睡眠の質も低下してしまいます。
例えば、深夜まで仕事をしたり、テレビを見すぎて就寝時間が遅くなると、睡眠時間が不足し日中眠気に襲われる。それにより日中に必要以上に眠ってしまい今度は夜眠れなくなる…という悪循環に陥ってしまうのです。
また、近年の働き世代に増えているのが『潜在的睡眠不足』。本当は体調がすぐれず、パフォーマンスも低下しているのに「自分は短い睡眠時間でも平気」と思い込んで無理を重ね、自覚のないまま睡眠不足に陥っている状態です。
普段は短時間睡眠なのに週末など休日に長時間睡眠をとるという方は注意が必要かもしれません。潜在的睡眠不足に陥っており、身体がサインを発している可能性があります。本当に短時間睡眠で問題ないなら、休日でも睡眠時間は変わらないはずです。
また、平日と休日とで睡眠時間に差をつけることで、体内時計がずれてしまうおそれも。体内時計を正常に保つためには十分な睡眠時間を確保した上で、起床・就寝時間を一定に保つことが大切です。必要な睡眠時間には個人差がありますが、成人の場合は平均6〜8時間程度とされているので目安にしてみてください。
光を抑えて寝る環境を整えよう

体内時計の調節に大きな影響を与えているのが光です。朝目覚め、目から光の刺激を受けることで体内時計は1日に1回リセットされます。そして本来は日没とともにあたりが暗くなることで睡眠に向けて身体が準備を始めます。
しかし、近年は夜も街が明るいため、光の刺激を絶えず受け続けることになります。そうなると、身体はまだ昼間だと勘違いし、体内時計を後ろにずらす調整をしてしまうのです。実はこれも寝つきを悪くする原因となっています。
体内時計のずれを防ぐことは睡眠にとって重要なポイントです。そこで、光の上手な使い方を櫻井教授に教えて頂きました。
1.いつも同じ時間に起き、光を浴びる
体内時計は起きてから光を浴びることでリセットされます。そのリズムを崩さないためにも平日と休日の起きる時間はなるべく同じにしましょう。どうしても平日で十分な睡眠が取れない場合は、1時間程度であればいつもより長く寝ても問題ないそうです。
また、睡眠不足の解消には移動中の電車や車、昼休み中の仮眠がおすすめです。仮眠は20分以内にすることがポイント。長時間の仮眠は身体が本格的な睡眠に入る体制を作ってしまい、起きた時にだるさを感じたり、夜に眠れなくなってしまったりするため、ご注意ください。
2.日没後はなるべく暗いところで過ごす
遅い時間の強い光は、身体が夜でも昼間だと錯覚を起こし体内時計のズレの原因となります。職場では難しいかもしれませんが、自宅では間接照明だけにするなど明るすぎない環境を作りましょう。
3.夜はテレビやスマホ、タブレットの使用を控える
テレビやスマホ、タブレットは画面を凝視するため、部屋の明かりといった環境光よりも直接的に目に強い光刺激を与えます。タブレットの使用で体内時計が2時間程度後ろにずれるという研究結果も出ているため、夜の使用はなるべく控えましょう。
4.昼夜逆転など、明るい場所や早い時間に寝る場合は光を遮る
明るい光は身体を覚醒に導いてしまいます。昼間など明るい環境で寝なければいけない場合は遮光カーテンなどで光を遮りましょう。それが難しい場合はアイマスクなどで目を覆うだけでも構いません。
睡眠はとても大切なもの。すこやかな眠りのために、質・量ともに十分な睡眠をとることを心がけましょう。
文/今井菜穂子
監修:筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 副機構長 櫻井武教授

関連するキーワード

今井菜穂子(いまいなほこ)
管理栄養士・遺伝子アドバイザー
株式会社谷田ヘルスリンク、渋谷DSクリニックにて栄養指導経験を積む。海外留学を経て現在はさくら内科クリニック(東京都世田谷区)にてダイエット、美容、健康に悩む方へ栄養・食事指導にあたる。ほか、食生活や生活習慣、美容、ダイエットに関する記事の執筆、監修。
公式HP:http://nahokoimai.com
※記事内の写真・文章・価格・人物などは記事の更新日時点での情報となります。
現在の情報と異なる場合もございますので、ご了承ください。
大塚家具のLINE公式アカウント!
続けて読みたい!あなたにオススメの記事