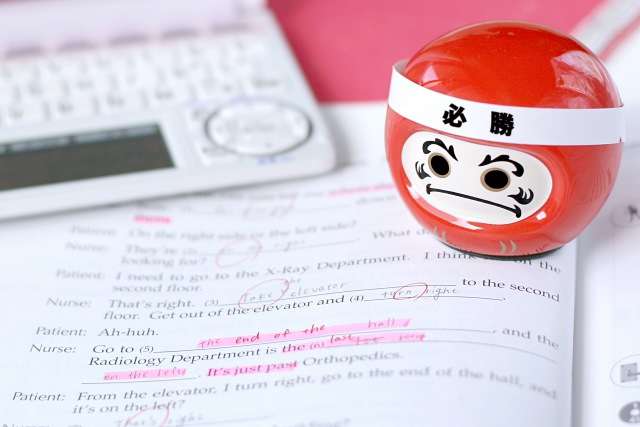ハーブで整える睡眠の習慣

最近なんだか寝つきが悪い。睡眠薬を飲むほどではないけれど、なんだかいつもと違う…。そんな経験はありませんか?日々のストレスにより自律神経が乱れ興奮状態になると、ベッドに入ってもなかなか寝つけない、寝ていても眠りが浅いといった睡眠障害に襲われやすくなります。病院に行くほどでもない場合は、まずはハーブと精油を生活に取り入れてみませんか?ホリスティックスクール ニールズヤードレメディーズ講師 鎮西(ちんぜい) 美枝子先生に睡眠習慣を整えるハーブと精油についてご紹介いただきました。
ハーブが与える睡眠への影響
睡眠は唯一、脳と身体を休めるためのものです。
睡眠はホルモンや自律神経の働きによって誘発されますが、疲れやストレスが溜まって自律神経が乱れると、睡眠も乱れてしまいます。ハーブにはこの自律神経を整える働きがあると言われています。そしてハーブは薬のように単一的な効果ではなく、自律神経・内分泌(ホルモンの調整)・免疫といったさまざまな方面から身体を整え、睡眠の質を改善する働きがあります。
睡眠に効果的なハーブティー3選

睡眠のためにハーブを取り入れたいと思っても、敷居が高いイメージがありませんか?まずは飲み物をハーブティーに変えてみるのが良いかもしれません。睡眠に効果のあるハーブティーはとてもたくさんありますが、その中でもクセがなく飲みやすいハーブティーを鎮西先生に三つ紹介していただきました。
①ジャーマンカモミール
よく耳にするカモミールですが、その歴史は長く古代エジプト時代から使われていたと言われています。リラックス効果が高く、炎症を抑える働きもあるため、ストレスからくる胃炎にも効果を発揮するそうです。甘い香りが眠りを誘い、ミルクと合わせても美味しく飲めます。
②リンデン
リンデンは木の名前で、その花と葉がハーブティーに使用されています。リラックス作用と穏やかな鎮静作用があります。花を使用しているため、香りも甘く飲みやすいお茶です。
③レモンバーム
レモンの爽やかな香りがするハーブティーです。心身の不調を抑えるだけでなく、整腸作用があるため緊張からくる胃腸の不調なども抑えてくれる働きがあります。他のお茶との相性もとてもよいため、ハーブティーが少し苦手な方もほうじ茶など飲み慣れたお茶に混ぜて飲むことができます。
ハーブティーを飲む際の目安は、200mlのお湯(カップ1杯)に対して茶葉を小さじ1加えます。お好みの濃さで3〜4分程度蒸らして飲むのがおすすめです。寝る1時間前くらいに飲むとよいそうです。毎日飲んでいると身体が慣れてしまい効果が薄れるので、同じお茶を続けて飲むのは2週間程度までとします。
また、茶葉はお茶として飲むだけでなく、ハーバルバスといった活用法もあります。日本に昔からある菖蒲湯やゆず湯のようにハーブをお風呂に入れる方法です。お風呂の温度では有効成分の抽出ができないので、ハーブを茶葉袋などに入れ、先にお湯で少し煮立たせてからお風呂にお湯とともに入れましょう。ハーブの入った茶葉袋でお肌のパッティングをすると、肌もツルツルになりおすすめです。飲むには少し古くなってしまった茶葉もハーバルバスとしてなら使えます。
睡眠に効果的な精油(エッセンシャルオイル)3選

ハーブティーの味が苦手という方は、アロマセラピーから取り入れることもおすすめです。アロマセラピーにはさまざまな種類の香りがありますが、今回はその中でも睡眠に効果の期待できるものを三つ教えていただきました。
①ラベンダー
リラックスの女王と言われるハーブです。その香りは心身のバランスをとり、副交感神経を優位にする働きがあります。
②マジョラムスイート
身体を温めて緩めてくれるようなリラックス効果の高いハーブ。植物の葉、根、茎を思わせる香りがします(専門的にはハーベイシャスな香りという表現を使います)。ラベンダーが苦手な方にもおすすめです。
③ネロリ
ビターオレンジの木の花の香りで、華やかで爽やかな香りです。悲しみやショックなど精神的な疲労からくる不眠に効果が期待できます。
精油(エッセンシャルオイル)は、アロマライトやディフューザーを利用してお部屋全体に香りを広げる使い方が一般的ですが、色々買ったり用意するのが大変な方はティッシュやコットンに精油を垂らしたりして、枕元に置いてあげるだけでも効果を得ることができます。また、アーモンドオイルやグレープシードオイルといった植物オイル小さじ2杯に精油を2滴ほど混ぜて、お風呂上がりに首回りやデコルテに塗っても香りを楽しむことができますし、リラックスした状態で入眠できます。ただし、精油は直接肌に塗ることはできません。肌に塗る際は必ず植物オイルに混ぜて使用しましょう。他にもバスソルトに垂らしてアロマバスにしたり、アルコールと精製水で作ったミストとして使用するなど使い方はさまざまです。香りは嗅覚に届くとすぐに脳にアクセスするため、自律神経・内分泌・免疫を整えてくれる働きがあるそうです。精油はなるべく新鮮なものがよいので、開封したら1年以内に使用することがおすすめです。
『なんとなく過ごしてしまうと、病気になったから病院に行き、お医者さんに言われたから薬を飲むといった、自分の身体なのに受け身になってしまいがち。でも、ハーブや精油を生活に取り入れ、自分の身体の状況を意識し、自分の健康状態を知ることが大切』と鎮西先生は言います。まずは自分の身体の状態に気づき、自然の力を借りて穏やかに身体を整えることが睡眠の習慣を整えることにも繋がっているのですね。
文/今井菜穂子
関連するキーワード

監修:ホリスティックスクール ニールズヤード
鎮西美枝子(ちんぜいみえこ)
AEAJ認定アロマセラピスト、AEAJ認定アロマテラピーインストラクター、JAMHA認定ハーバルセラピストJAMHA認定ハーバルプラクティショナー、フラワーエッセンスプラクティショナーなど。自身の体調不良をきかっけに植物療法と出会う。講師歴は18年目を迎え、確かな知識と明るい人柄で生徒からの信頼が厚い。フレグランスやハーブに精通し、初心者の人にもわかりやすい講座で大人気。
※記事内の写真・文章・価格・人物などは記事の更新日時点での情報となります。
現在の情報と異なる場合もございますので、ご了承ください。
大塚家具のLINE公式アカウント!
続けて読みたい!あなたにオススメの記事