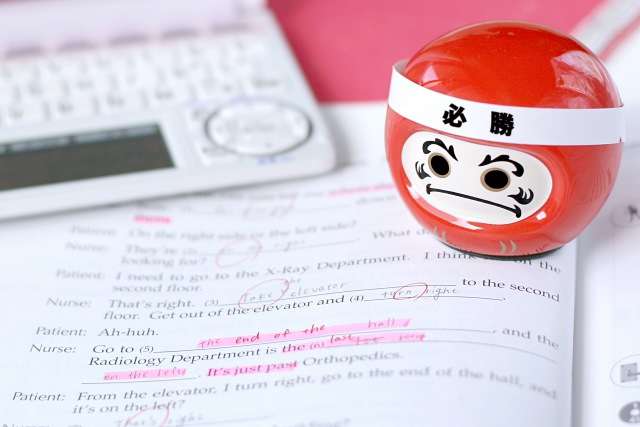夏の寝苦しい夜を乗り切ろう!身体の熱を出す食品5選
COLUMN

夏は気温や湿度が高まり、蒸し暑くて寝苦しい季節。気候だけではなく、夏は日差しが強いため、日中太陽から吸収した熱が身体にこもりやすくなる季節でもあります。本来睡眠中は体温が下がることで鎮静状態になりますが、身体に熱がこもってしまうと興奮状態が続き、寝苦しさが倍増してなかなか寝つけないなんてことも。
東洋医療の1つである薬膳には、身体の熱を出す食材を食べることで夏を乗り切るという考え方があるそうです。今回は薬膳に基づき、身体の熱を抑える食品5つをご紹介します。
食材には身体を温めるものと冷やすものがある?
薬膳では、食材には「四性」(熱性、温性、(平性)、涼性、寒性)があると考えられています。つまり、食材にはそれぞれ体を温める性質を持つものと体を冷やす性質を持つものがあるということです。例えば香辛料は「熱性」や「温性」のものが多く、身体を温めます。逆に夏野菜は「涼性」や「寒性」といった身体を冷やす性質を持つことが多いと言われています。
これは科学的根拠ではなく、古代からの長年の経験によって分類されているそうですが、香辛料である唐辛子に含まれるカプサイシンや生姜に含まれるジンゲロールやショウガオールといった栄養素は血行を促進し身体を温める働きがあります。一方で夏野菜に多く含まれる栄養素であるカリウムは利尿作用があり、余分な熱や水分を体外に排出するため、きちんと理にかなっているのです。
四性の考え方で分類すると、食材は「熱性」がもっとも温める性質が強く、続いて「温性」、温める性質も冷やす性質もないものが「平性」、もっとも冷やす性質が強いものを「寒性」、「寒性」ほどではないものの冷やす性質のあるものを「涼性」とされています。
身体を冷やすことはよくないと思われがちですが、薬膳では季節や身体の状態に合わせて食材を選ぶことが体調管理のポイントだと言われています。そのため、暑い夏、寝苦しいと感じるときは「涼性」や「寒性」といった身体の熱を抑える食材を意識的に食べてみましょう。
旬の食材は身体の味方
薬膳では、「旬」という言葉が指す意味は2つあります。1つは、食材は「旬」の季節になると栄養分が増え、最も美味しくなるということ。そして、もう1つは「旬」の季節に合わせて食べると健康に良い効果があるということ。実際に冬が旬の食材は「温性」や「熱性」のものが多く、夏が旬の特に夏野菜は「涼性」「寒性」が多い傾向にあります。
四季のある日本では、季節の変化にしたがって人間のバイオリズムも変わるため、旬の食材を意識的に食べることが、実は自然と体調管理につながっているのです。ハウス栽培などのおかげで1年中様々な果物や野菜が手に入るようになりましたが、なるべく「旬」を意識して食材を選んでみましょう。
寝苦しい夏におすすめ!身体の熱を出す食品5選
夏の暑さで寝苦しいと感じるのは身体が熱を溜め込んでいるサインかもしれません。身体の熱を外に出すために今までお伝えした薬膳の考え方に基づいて、夏に「旬」を迎える「寒性」「涼性」とされる食品を5つ抜粋してご紹介します。
トマト
太陽のように真っ赤なトマトは代表的な夏野菜です。四性分類では「微寒性」で「寒性」と「涼性」の間くらいに位置します。また、薬膳では「解暑清熱(かいしょうせいねつ」といって身体にこもった余分な熱を収め、暑気あたり(夏の暑さのために身体を壊すこと)を解消する効果があると言われています。
なす
こちらも夏野菜で四性は「寒性」です。なすの「寒性」は夏野菜の中でも特に強いと言われ、胃腸が弱いなど、もともと冷えを感じやすい方は逆に身体を冷やしすぎてしまうこともあります。心配な場合は生姜など身体を温める働きのある食材と合わせて食べることで調整しましょう。
きゅうり
いつでも見られる野菜ですが、きゅうりは立派な夏野菜です。今でも夏の京都や山登りに出かけると氷水を張ったタライに入った「冷やしきゅうり」が売られていることがあります。四性では「涼性」に分類され、トマトと少し似ていますが「清熱」という身体にこもった余分な熱を収める働きがあるとされています。
スイカ
スイカと夏はセットでイメージされるように、こちらも夏野菜(果物)です。四性は「寒性」に分類されます。水分を多く含むだけでなく、カリウムが豊富に含まれるため利尿作用が強く、身体の熱を外に出してくれます。
メロン
スイカに隠れてしまいがちですが、メロンも夏が旬の果物です。四性は「寒性」に分類され、スイカ同様カリウムが多いだけでなく、シトルリンという肝臓内で尿素の形成を促進する高い利尿作用があり、身体の熱を外に出してくれます。
今回は「旬」に着目して野菜や果物を中心にご紹介しましたが、「涼性」「寒性」の食材は他にも、はと麦や小麦、砂糖、そばといった炭水化物の食材もあります。どれもスーパーや八百屋で簡単に手に入る食材を中心にご紹介しました。
ついつい同じものばかり買ってしまいがちですが、季節や体調に合わせて選ぶという方法があります。暑さで寝苦しい夜は「寒性」や「涼性」の夏が「旬」の食材を意識して美味しく対策してみましょう。
参考文献:
「東方栄養新書」(株式会社メディカルユニコーン)
関連するキーワード

今井菜穂子(いまいなほこ)
管理栄養士・遺伝子アドバイザー
株式会社谷田ヘルスリンク、渋谷DSクリニックにて栄養指導経験を積む。海外留学を経て現在はさくら内科クリニック(東京都世田谷区)にてダイエット、美容、健康に悩む方へ栄養・食事指導にあたる。ほか、食生活や生活習慣、美容、ダイエットに関する記事の執筆、監修。
公式HP:http://nahokoimai.com
※記事内の写真・文章・価格・人物などは記事の更新日時点での情報となります。
現在の情報と異なる場合もございますので、ご了承ください。
大塚家具のLINE公式アカウント!
続けて読みたい!あなたにオススメの記事