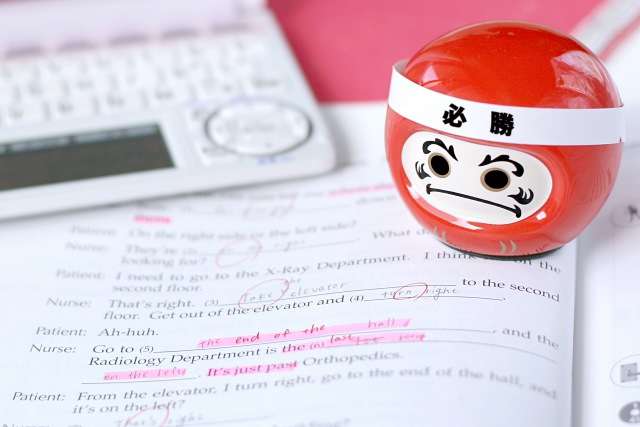睡眠中の“歯ぎしり”見過ごさないで!原因と対策を探る
COLUMN

最近、朝起きると顎に違和感を感じるということはありませんか? もしかするとそれは、“歯ぎしり”が原因かもしれません。自分では気づきにくい歯ぎしりですが、ベットパートナーの睡眠を中断させていることも。歯にも大きな負担がかかる睡眠中の歯ぎしりについて調べてみました。
歯ぎしりの種類と歯にかかる負担
歯ぎしりには下記の3種類があると言われています。
【グライディング】
上下の歯を横に擦り合わせギリギリと音を鳴らす。歯ぎしりの中で最も多く見られるタイプ。
【クレンチング】
ほとんど音を立てずに、上下の奥歯を強く噛みしめるタイプ。
【タッピング】
上下の歯を小刻みに打ち鳴らすタイプの歯ぎしりで、あまり見られない。
上記のうち、気をつけなければいけないのは無音のクレンチングと、横にギリギリするグライディング。人は起きているときは、どんなに強く噛みしめても無意識に力は制御されますが、睡眠時は制御機能が働かなくなるため、歯ぎしりすることで歯や顎には相当な負荷がかかってしまうのです。このときに歯にかかる力は、自分の体重の約2倍にもなると言います。
睡眠中の歯ぎしりはストレス発散のための行為!?
歯ぎしりが起こるメカニズムについては、未だ完全には解明されてはいません。しかし、噛み合わせの悪さ、遺伝、飲酒、喫煙、逆流性食道炎や睡眠時無呼吸症候群などの疾患、抗うつ剤の服用、ストレスが原因だと言われています。
なかでもストレス性の歯ぎしりが多いのではないかと考えられています。
このことを裏付ける興味深いマウス実験(※1)があります。
・歯ぎしりをする
マウスを仰向けにして動けない状態で固定し続けると、ストレスを受けた状態になり100%のマウスが胃潰瘍になった。
・歯ぎしりをしない
別のマウスを同様に固定して、今度は口に木片を噛ませて食いしばりができるようにさせると、胃潰瘍の発生率は66.7%に減少した。
この実験から、マウスはストレスを受けた心身を守るために、歯ぎしりを行っているとも言えます。また、マウスを冷蔵庫に入れ体を冷やす実験では、木片を噛んでいるマウスは噛んでいないマウスより体温低下が少ないという結果になりました。
歯ぎしりが及ぼす身体へのダメージと改善方法
睡眠中の歯ぎしりはストレスを解消する役割がある反面、過度の歯ぎしりは、歯が削れ、割れることも。歯を保護してくれるエナメル質が破壊される悪影響もあるので注意が必要です。知覚過敏、腰痛・肩こりを引き起こす可能性も考えられます。また、歯・口の中以外にも、美容面でもダメージを受けます。歯ぎしりをすることで顎の筋肉を常に動かしているので、顎周りの筋肉が発達し顔が大きくなったり、エラが張ってしまうこともあるそうです。
睡眠中に歯ぎしりをしないようにするには、下記の点に注意しましょう。
・運動・ストレッチをしたり、寝る前に好きなことをする時間をつくるなど、自分に合ったストレス解消法を見つけよう。
・お酒やタバコはできるだけ量を控えるようにして生活習慣を見直そう。
睡眠中の歯ぎしりは、ベットパートナーに不快な思いをさせるだけでなく、自分の身体にも悪影響を及ぼす場合があります。歯ぎしりの治療をしてくれる歯科医院もあるので、気になることがある場合はなるべく早く診察を受けるようにしましょう。
【参考文献】
・デンタルヘルス通信「歯ぎしりが気になっている方へ ~歯ぎしりの原因・予防方法について~」
http://i-scdc.jp/blog/?p=129
・カラダ研究所「心身の状態に現れる!?睡眠時の歯ぎしりの役割と危険性」
https://www.mrso.jp/colorda/lab/1060/
※1 http://ajpregu.physiology.org/content/279/6/r2042
文/高橋晴美
関連するキーワード

高橋晴美(たかはしはるみ)
フリーランス編集ライター。食と健康・旅をテーマに執筆。
主に、旭屋出版 日経BP社 夕刊フジ JTBパブリッシングの月刊誌およびMOOKSなどの編集記事・広告を担当。(株)スミフルジャパンのバナナソムリエ。ベジフルティーチャー。
大塚家具のLINE公式アカウント!
続けて読みたい!あなたにオススメの記事